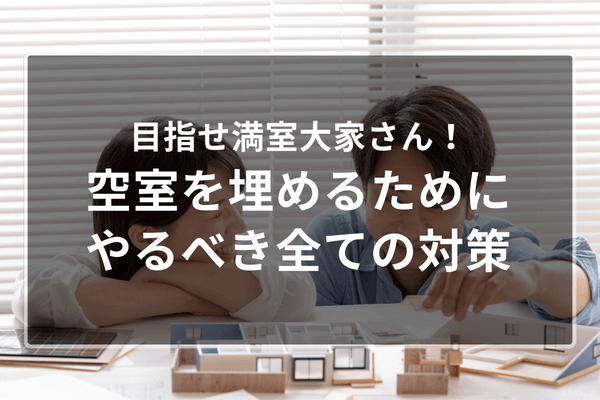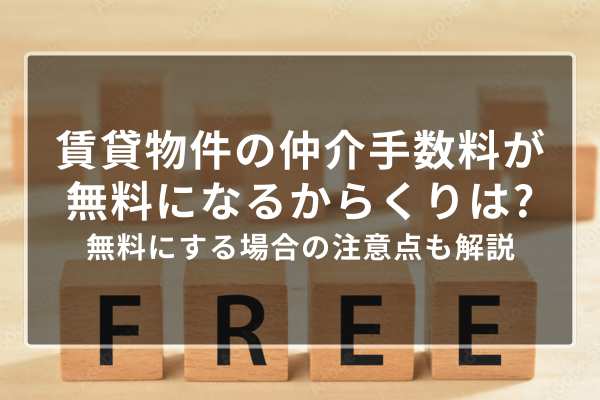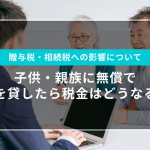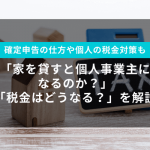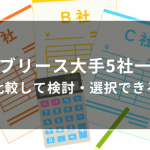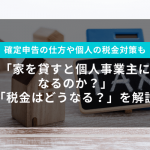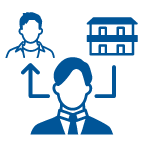マンションの大規模修繕を検討すべき3ポイントと費用調達方法3タイプ
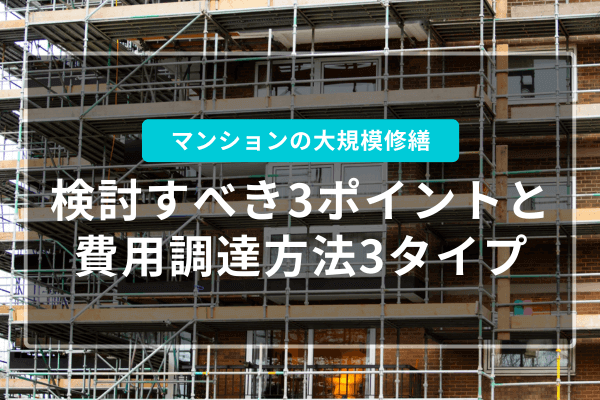
経営するマンションの維持管理のためには、日々の点検管理以外に、大規模修繕と呼ばれる大掛かりなメンテナンスも必要です。しかし、どのタイミングでどこに施工すべきか、工事はどこに頼むべきなのかなど、わからないことが多すぎて不安に感じているオーナーも多いかと思います。
本記事では、大規模修繕を検討するタイミングと内容、資金調達などを含め、経営中のマンションに適切な大規模修繕をするために、オーナーが知っておくべきことを、やさしくまとめてあります。
この記事の内容
1.マンションの大規模修繕を検討する3ポイント
マンションの大規模修繕とは、建物の経年劣化に対応し、建物内部・外部の状態を維持することです。「大規模修繕」という言葉は一般的に使われていますが、大規模修繕という工事方法や商品があるわけではなく、
必要に応じた計画的な修繕のことを、まとめて大規模修繕と呼んでいます。
マンションの劣化は、放置しておくと不具合がひどくなり、最悪のケースでは、住めなくなってしまうほどのトラブルにつながることがあります。そのような事態にならないようにするためには、計画的な点検をして、修繕が必要な箇所には早めに手を入れていく必要があります。大規模修繕で手を加えるべきポイントは以下の3つです。
- 物理的な劣化 見た目・性能・安全性
- 社会的な劣化 入居者ニーズ・時代・環境
- 経済的な劣化 修繕費・管理費・資産価
1-1.物理的な劣化 見た目・性能・安全性
コンクリート躯体のメンテナンス、設備の配管劣化・腐食などの経年劣化に対応します。修繕や改修によって物理的に修復ができるので、計画点検によって建物の性能や安全性を確認・確保できます。
たとえば、外壁のクリーニング・防水防汚塗装・ヒビ割れの修復・給排水管や古くなった設備の取り換えなども含め、見た目と機能の両方を保全します。建物の安全性と、空室対策に直結する部分でもあるため、3つの中で最優先するべきポイントです。
1-2.社会的な劣化 入居者ニーズ・時代・環境
間取り・デザイン・設備などが時代遅れになり、周辺エリアのライバル物件の中で、相対的に物件価値が低くなることへの対応です。また、長い経営期間の間に法令の変更が起こり、結果的に不適格な物件になってしまっていることへの対応も含まれます。
昨今は、経年した建物に適度な手を入れたマンションを「ヴィンテージマンション」と呼び、若い方にも人気があります。そのため、経営中のマンションが世間のトレンドや生活様式の変化から、どのくらい乖離しているのかは、客観的な視点が必要です。
空室率が20%以下の状態であれば、大規模修繕は数年の先送りをしながら、様子を見ていくのでも、問題はありません。数々の現場を見てきている、不動産管理会社の担当者の意見も参考にしてください。
1-3.経済的な劣化 修繕費・管理費・資産価値
マンションの資産価値は、売却価値が修繕費用を上回ると、経済的劣化をしていると判断します。好景気で新築時価格の2倍や3倍で売れるときは、経済的劣化は遅くなり、経済が低迷して売却額が下がると、経済的な劣化が促進すると考えます。
たとえば、現時点で売却額が1億円、大規模修繕費が1.1億円であれば、その物件は経済的に1割の劣化をしていることになります。オーナーにとっては大切なことなのですが、入居者にとってはあまり関心のない部分でもあります。
ローン返済がなければ、一時的な経済的劣化が起きても、インフレによってトータルでバランスを取ることもできます。しかし、不動産は必ず築年による劣化が起きますので、いつかは建物が経済的劣化をした状態になります。適切なタイミングで大規模修繕をしていくことにより、劣化速度を遅くすることができます。
はじめての大規模修繕で、ご自分のマンションに、何の工事が必要で、何からはじめればよいのかわからないオーナーは、経験値の高い不動産管理会社に相談をしてみることからはじめてください。
NTTデータグループが運営する「賃貸経営HOME4U」の一括無料相談サービスなら、大規模修繕のスムーズなサポートしてくれる会社が見つかります。一度の入力で複数社に請求ができますので、プランの比較もカンタンです。
賃貸経営・土地活用の
相談をしたい方はこちら
複数の会社にまとめて相談
2.大規模修繕の費用めやすとタイミング
本章では、大規模修繕費用のめやすと修繕計画のタイミングをまとめ、各箇所にどのような工事をするのかを説明します。基本的に、築年数に対応してタイミングが発生します。費用は、マンション経営をスタートする時点(新築時点)で、築30年までの長期修繕計画を作り、年次計画に沿って資金準備するのが一般的です。
国土交通省の発行する民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブックによれば、鉄筋コンクリート造マンション1LDK・20室を経営している場合の、修繕タイミングと費用は以下のようなイメージです。
【鉄筋コンクリート造マンション 1LDK 20室】
| 築年数 | 修繕箇所 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|---|
| 5~10年 | ベランダ・階段・廊下(塗装)
室内設備(修理) 排水管(高圧洗浄等) | 約9万円/戸 |
| 11~15年 | 屋根・外壁(塗装)
ベランダ・階段・廊下(塗装・防水) 給湯器等(修理・交換) 排水管(高圧洗浄等) | 約55万円/戸 |
| 16~20年目 | ベランダ・階段・廊下(塗装)
室内設備(修理) 給排水管(高圧洗浄等・交換) 外構等(修繕) | 約23万円/戸 |
| 21~25年目 | 屋根・外壁(塗装・葺替)
ベランダ・階段・廊下(塗装・防水) 浴室設備等(修理・交換) 排水管(高圧洗浄) | 約116万円/戸 |
| 26~30年目 | ベランダ・階段・廊下(塗装)
室内設備(修理) 給排水管(高圧洗浄等・交換) 外構等(修繕) | 約23万円/戸 |
| 大規模修繕費合計金額/1戸あたり | 約225万円/戸 | |
| 大規模修繕費合計金額 合計金額 | 約4,490万円/一棟 | |
【参照:国土交通省「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」】
全体のサイクルとしては築10年目以降から、5~10年のタイミングで、まとまった修繕費用が発生することがわかります。上記表では30年までしか記載がありませんが、鉄筋コンクリート造マンションの法定耐用年数は47年あるため、31年目以降も修繕は続きす。
基本的なメンテナンス内容は変わらないため、木造や鉄骨造の大規模修繕費用が、鉄筋コンクリート造に比べて格段に安くなるというわけではありません。以下は、具体的にどこにどのような工事をするかの説明です。
- ベランダ、階段、廊下
- 外壁・屋上・外構
- 室内設備
- 給排水設備
2-1.ベランダ、階段、廊下
ベランダ・階段・廊下は共用部分であり外部に面していることから、早く劣化し始めます。メンテナンスは主に防水工事です。適切なタイミングで工事をしないと、建物の劣化速度が早まります。
たとえば、防水効果が低下してくると、雨が降るたびに水たまりができるようになります。コンクリートが水を吸って水はけも悪くなるため、共用部にカビ・サビなどが発生しはじめます。雨のない日も入居者によって床面は汚れていますので、土やホコリなどのヨゴレもしみ込んでいきます。
放置しておくと、コンクリートの表面に藻やコケが生えて滑りやすくなり、転倒による大きな事故の要因になります。鉄製部分にはペンキ塗装、タイル部分の損傷には貼替が必要です。
2-2.外壁・屋上・外構
構造に関わらず、建物は一年中、紫外線・雨風を受けていますので、建物の外側にある外壁・屋上・外構は、日々、劣化が進みます。特に、外壁と屋上(屋根)の修理修繕を怠っていると、次第にひび割れ・破損ができ、建物に雨がしみ込み、雨漏りにつながっていきます。
明確にわかるほど雨水が漏っていなくても、じわじわと建物に水分がしみ込んでいけば、白アリやカビの発生、コンクリート・木材・金具の腐食を引き起こします。その結果、大きな水漏れ・建材の落下・耐震性の低下など、構造によってさまざまなトラブルの原因となります。
一番良くないのは、仮に大きな事故が起きなかったとしても、確実に建物の寿命を縮めてしまい、資産価値が低下することです。
外構とは、敷地内にある門・車庫・カーポート・土間・アプローチ・塀・柵・垣根などのことです。外構の劣化は直接的に物件に影響を与えませんが、外構が朽ちてくると落下や倒壊の事故の可能性が高まるうえに、見た目が悪くなるため、空室リスクが高まります。劣化した外構をすぐに修繕できない場合は、撤去を検討してください。
2-3.室内設備
室内設備とは、 内装およびキッチン・トイレ ・バス・ 洗面所・棚・クローゼット・室内照明・Wi-Fiなどの回線のことです。どれも経年劣化によって、徐々に故障や修理が必要になっていきます。
メンテナンスによって寿命を長くすることは可能ですが、実際に使うのは入居者であるため、法定耐用年数前後で交換することになります。退去が発生したときの原状回復時に点検をして、必要なメンテナンスと交換などを行うのが一般的です。
2-4.給排水設備
給排水設備は、生活に必要な水を建物内に供給する設備のことです。たとえば、給水管・貯水槽(貯水タンク・給水タンク)・給水ポンプ・給湯設備などです。排水設備は、使った水を排出するための設備で、配水管・通気管・排水槽・排水ポンプ・浄化槽などのことです。また、雨水を排出するための雨樋・雨水パイプなども排水設備です。
どちらも生活の要となる設備であるため「トラブルがない」ことが大前提であり、定期点検とメンテナンスが不可欠です。点検には有資格者によるチェックが必要であり、建物の規模や構造によっては、年間の定期点検が義務づけられています。
給排水設備の法定耐用年数は15年ですので、設備に異常がなくても、大規模修繕のタイミングに合わせて修繕・更新を検討してください。給排水設備のメンテンナンスを放置しておくと、生活用水が使えなくなる、汚水が流れなくなるなど、普通の暮らしができない状態を引き起こします。さらに、給排水のトラブルによって二次的な事故や病気が発生した場合には、オーナー責任を問われる可能性があります。
【参照:法定耐用年数】
3.マンションの大規模修繕費用3つの調達先
大規模修繕費の調達方法を3つにわけて説明します。大規模修繕は長期修繕計画に沿って行いますが、カスタマイズ性の高い建物管理方法でもあるため、費用調達の状態に合わせて、最優先するべきところにメンテナンスをする、という考え方で問題ありません。資金準備の方法は以下の3つです。
- 積立資金
- 借り入れ・共済
- 補助金・助成金を活用する
3-1.積立資金
オーナーが自分で行う、賃料収入からの預金や積立金です。賃貸物件には、分譲マンションのような管理組合がないため、入居者から修繕積立金の徴収がありません。そのため、修繕積立金相当を含んだ賃料設定したうえで、敷金や礼金なども活用しながら、定期預金・金銭信託・小規模企業共済など、経営規模に合った無理のない資金準備をしていきます。
大規模修繕費を賃料に含むためには、先に長期修繕計画を作り、必要な金額を算出します。賃貸物件の運営に関した決定権はオーナーにありますので、国土交通省の「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン」を参考にしながら、ご自分の裁量で決めることもできます。
しかし、大規模修繕には専門的な内容が多く、施工に関しては多岐にわたる専門会社との連携が必要となるため、不動産管理会社に建物管理の委託をし、長期修繕計画プラン・資金計画を一緒に準備していく方がスムーズです。
【参照:「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン」】
3-2.借り入れ・共済
準備していた金額で修繕費が足りない場合は、個人の預貯金からの持ち出しか、借入をします。借り入れ先は、住宅金融支援機構の一部の商品か、民間金融機関になります。
大規模修繕費用のための金融商品はあるのですが、ほとんどが、管理組合のある分譲マンションへの融資が条件であるため、個人オーナーは、まずは、複数の金融機関への相談をしてください。
また、2021年には賃貸オーナーの大規模修繕資金確保の課題解決を目的とした「全国賃貸住宅修繕共済協同組合」が発足しています。この組合の共済制度に加入すると、修理修繕の必要な金額とタイミングに応じて、最長50年目まで共済費が支払われます。積立金はかかりますが、年間必要経費として計上できますので、前項の積立などに使っていた費用の一部を、共済に切り替えるなども検討してください。
【参照:住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資(長期耐用耐震改修)】
【参照:共済 国土交通大臣認可 賃貸住宅修繕共済】
3-3.補助金・助成金を活用する
マンションの大規模修繕に使える補助金があります。代表的なものは以下の5種類ですが、それ以外にも、地域で用意している補助金・助成金などもあります。
| 補助金名 | 補助内容 |
|---|---|
| アスベスト除去等事業補助金 | 壁などに吹付けられたアスベストの分析調査や除去などの工事にかかる費用を補助 |
| 劣化調査診断費補助金例:文京区 | 大規模修繕を前提とする劣化調査に関する費用を補助。物件のある自治体によっては管理組合のみが対象になる |
| 耐震改修費用補助金 | 耐震改修工事費用の一部を補助 |
| 省エネ対策等補助金 | エネルギーの地産地消に向けて省エネ対策費用を補助 |
| エレベーター防災対策改修補助金 | エレベーターの安全確保のためにエレベーター改修費用を補助 |
利用できる制度は自治体・市町村まで含めると多岐にわたっており、工事前に申請する必要があります。自治体によって少しずつ制度の内容に違いがありますので、よく確認をしたうえで申し込みをしてください。大規模修繕を含めた建物管理を委託していれば、不動産管理会社が調査をしたうえで、使える補助金や助成金の提案・申請代行もしてくれます。
大規模修繕と資金計画に不安がある方は、不動産管理会社に大規模修繕に関した相談をしてみてください。その際には、なるべくたくさんの建物管理プランを比較し、担当者とも面談をしたうえで、判断をしていきます。
NTTデータグループが運営する「賃貸経営HOME4U」の一括無料相談サービスなら、一度の入力で複数社に請求ができますので、プランの比較もカンタンです。各社の提案で気になるものがあれば、担当者と面談することで、より具体的な話ができます。
今現在、入居者募集などの賃貸管理をどこかに委託している場合でも、大規模修繕や建物管理は、別の会社に頼むことができます。今の会社も含め、会社をたくさん比較することによって、最善の回答を得ることができます。
4.大規模修繕までの大きな3つの流れ
経営中のマンションに大規模修繕を行うまでには、次のような3つの流れがあります。賃貸マンション経営の場合、物件全体はオーナー所有となるため、分譲マンションにみられるような管理組合は存在していません。
そのため、管理組合がやる仕事は、不動産管理会社に委託をして、大規模修繕と資産維持を、オーナーと管理会社が二人三脚ですすめていくことになります。
- 長期修繕計画を立てる
- 点検・検査・診断
- 計画修繕を随時進行
4-1.長期修繕計画を立てる
長期修繕計画とは、10年後・20年後・30年後にはどのようなメンテナンスが必要で、それにはいくら必要かを想定したものです。
修繕計画がない状態でお金を準備しても、金額に根拠がないため、状況によっては資金が足りなくなり、借り入れをする必要が出てきます。万が一、融資が下りなかった場合は、必要な修繕が十分に行われない可能性もあります。
長期修繕計画は、経営スタート時点で作成してあるのが理想ですが、大規模修繕が気になり始めたときから作成するのでも問題ありません。長期修繕計画は、国土交通省のガイドラインを参考にしながら作成するのが一般的です。
ガイドラインに沿うことは絶対ではありませんが、多くの不動産管理会社がこのガイドラインをベースに作成しますので、会社を変更しても内容が伝わりやすく、トラブルも起きにくいと言えます。
【参照:「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン」】
4-2.点検・検査・診断
長期修繕計画が出来たら、計画に沿って工事が必要だと思われる箇所を点検し、建物の現状を検査・診断していきます。点検・検査・診断には有資格者が必要なので、資格者が在籍する不動産管理会社に管理委託をするか、不動産管理会社から資格者を、有料で派遣してもらう必要があります。
この時点で、まだ必要ないと診断された工事は、点検スケジュールの再編をします。反対に、日常的な点検作業の中で、予期しなかった不具合が発見されれば、修繕計画の前倒しをします。管理会社による点検以外にも、住人からのクレームで不具合が発覚することもあります。
このように、長期修繕計画はあくまで「計画」なので、現状に即したものに、随時、上書き更新していく必要があります。
2-3.計画修繕を随時進行
毎年、長期修繕計画に則って、必要なことをすすめていきます。大まかなイメージとして、1回目の大規模修繕は新築時の状態に戻すタイプの工事、2回目は耐用年数を超えた建具・設備類の不具合を修理修繕し、時代に合わせた性能向上を目指します。3回目以降は、給排水などの建物インフラ設備に手を加えて、建物全体の現状維持を図るのが目的です。
さらに、3回目以降は耐震補強や省エネ対策なども検討する必要があり、オーナーは資金計画で頭を悩ませることが増えていきます。しかしながら、分譲・賃貸ともに、大規模修繕費用が潤沢にあるマンションは、ほぼないと言えますので、状況と相場に合わせて、適宜な判断をしていくしかありません。どのタイミングでどこまでやるのかは、オーナーの裁量で判断します。
マンション経営そのものが順調であれば、必要な資金は準備できますので、不動産管理会社と相談をしながら、満室経営を目指すことで、大規模修繕の問題はクリアしていくことが可能です。
5.マンションの大規模修繕費用に関した5つの素朴なQ&A
マンションの大規模修繕が気になり始めると、以下のような疑問が頭に浮かぶと思います。今回は、大規模修繕に関した素朴な疑問をQ&A方式で集めてみました。
Q1.大規模修繕って、どうしてもやらなきゃだめ?
Q2.お金がなくて大規模修繕ができません
Q3.他のオーナーってどうやって修繕費用を準備してるの?
Q4.修繕のための積立って経費にできないと聞いたのですが
Q5.大規模修繕ってどこに依頼すればいいの?
Q1.大規模修繕って、どうしてもやらなきゃだめ?
A:資産価値維持のためにはするべき。不具合放置は経営リスクが高くなる
大規模修繕をしないままでいると、見た目がキレイでも、内部で劣化が進んでいき、大きな不具合が起きる可能性が高くなります。大規模修繕はギリギリまで先延ばしにすることもできますが、周辺のライバル物件が定期的な大規模修繕をしていれば、築年が進むごとに、外観や住み心地などに差がついてしまい、空室リスクが高まります。
マンション経営の収益が落ちてしまうと、大規模修繕のための資金をプールするのも難しくなるため、大きなトラブルが発生した時に必要な費用を確保できず、さらに劣化が進む可能性があります。こうなると、築年よりもかなり劣化した物件となるため、資産価値そのものが下がります。
運よく、何も不具合が起きていなくても、建物は必ず経年劣化しますので、いつかは大規模修繕をやらなければならないタイミングが来ます。長期修繕計による定期点検・メンテナンスをしながら、適切なタイミングで大規模修繕をするようにしてください。
Q2.お金がなくて大規模修繕ができません。
A:銀行融資や共済の利用ができます。
大規模修繕が必要になるのは、主に築10年目以降からなので、それまでの期間に、賃料収入から資金を準備しておきます。いつ、どのくらいの金額が必要なのかは、長期修繕計画があればわかります。
資金が足りない場合は、金融機関からの融資、または共済の利用ができます。金融機関には複数の大規模修繕ローン商品がありますが、管理組合を対象にしたものが多いため、個人のオーナーの場合は、個人相談に行くことをおすすめします。
また、2021年に発足した「全国賃貸住宅修繕共済協同組合」の共済に加入すると、個人のマンションオーナーでも、管理組合の修繕積立金のように、共済費を積み立てておくことができます。加入1年後から、毎年実施する定期検査を行い、所定のチェックリストに該当する劣化が確認された場合には、修繕工事のための共済金請求ができます。
【参照:全国賃貸住宅修繕共済協同組合】
Q3.他のオーナーってどうやって修繕費用を準備してるの?
A:管理会社に積立依頼か、オーナーが自主積立をしていることが多い
大規模修繕のための資金準備方法は、オーナーによってさまざまです。一般的には、貯金や積立をしながら、必要な場合は融資を検討しています。個人オーナーの場合、大規模修繕のためというよりも、必要な修理修繕が起きたときのために、普段から資金を用意しておくという考え方が強いと言えます。
不動産管理会社に建物管理を委託している場合は、管理会社が賃料から、あらかじめオーナーと決めた%をプールして積み立てているケースもあります。マンション経営以外にも事業をしているオーナーの場合は、あえて積み立てはせず、必要なときの資金調達のめどをつけているケースもあります。
どのケースでも、大規模修繕資金のための資金が潤沢に用意されていることは少なく、できる範囲での修繕を行っている傾向があります。
【参照:国土交通省住宅局「民間賃貸住宅の大規模修繕等に対する意識の向上に関する調査検討報告書」】
Q4.修繕費のための積立は経費にならないと聞いたのですが
A:単なる積み立ては経費になりません。修繕共済加入なら経費にできます
修繕費のために自分の口座で定期や積み立てをしても、マンション経営の経費にはなりません。会計のルール上、経費というのは、実際に発生したときに適用する項目です。
大規模修繕は未来の工事のためのお金であり、絶対に使う予定のお金なのですが、その年に工事が発生しないのであれば、その年の経費に計上することができません。たとえば、1,000万円を資金として積み立ておいても、会計・経理上は収入となってしまい、使えないお金なのに税金が発生してしまうのです
このことから、他で資金調達ができるオーナーは、あえて積み立てをせずに、必要な場合は融資を受けるというスタイルをとる方もいらっしゃいます。ただし、2021年に発足した、賃貸住宅修繕共済という制度に加入すると、毎年の掛け金は経費となり、大規模修繕に必要な金額を共済から支払ってもらうことができます。
【参照:国土交通大臣認可賃貸住宅修繕共済】
Q5. 大規模修繕の工事ってどこに依頼すればいいの?
A:不動産管理会社に依頼するのが一般的。でも見積比較は必要です
大規模修繕を検討しはじめたら、まずは、今現在、管理委託をしている不動産管理会社への相談をしてみてください。契約中の管理会社は、担当者がマンションと入居者の現状をよく理解していますので、話が通りやすいと言えます。今までの修理修繕やトラブル対応の実績があるうえに、日常管理によって、建物の劣化状況や、不具合状況なども把握しています。
管理会社に大規模修繕工事を委託する場合は、管理会社が工事の元受けとなり、企画・設計から工事までを一貫して施工会社に発注する、責任施工方式を取るのが一般的です。
それ以外の方法としては、オーナーがご自身で施工会社を探して、個別に大規模修繕の工事依頼することもできます。しかし、大規模修繕の点検・診断・施工には有資格者が必要になるため、適切な会社を選ぶには、不動産業界と建設業界に、ある程度の知見やネットワークが必要です。
1つの工事内容でも、複数の工程を行う会社・職人が複雑に絡み合うことが多く、知識や人脈のない状態で依頼をすると、中間マージンによって必要以上に費用がかかってしまう可能性があります。このようなことから、どこに依頼をするのであっても、かならず複数のプランを比較するようにしてください。
国土交通省が行った「マンション総合調査」によれば、大規模修繕工事に関して、外部の専門家に依頼を検討したいと考える管理組合は、全体の約35%とかなり高い数字が出ています。また、コンサルティングだけでも受けたいは、全体の6割を超えており、大規模修繕に関したノウハウや、頼りにできる相談先が少ない現状が浮き彫りになっています。
賃貸マンション経営には管理組合がありませんが、大規模修繕への知識やノウハウ不足、そして大規模修繕を成功させることへの不安は、個人オーナーも管理組合も同じだと言えます。大きな資金を使って、大きな工事をする大規模修繕工事には、頼りになる管理会社の存在が必要です。
NTTデータグループが運営する「賃貸経営HOME4U」の一括無料相談サービスを活用し、今の管理会社を含めて、たくさんの管理会社のプランを比較することで、最善の選択ができるようになります。
【参照:令和5年度マンション総合調査結果からみたマンションの居住と管理の現状】
まとめ
マンションの大規模修繕とその費用に関してまとめました。大規模修繕にかかる費用は、10年サイクルで発生し、かなりのまとまった金額になることがわかりました。費用の捻出方法は、定期預金などでコツコツ作る、融資を受ける、共済を利用するなど、オーナーによってさまざまでした。また、補助金や助成金を利用することもできます。
大規模修繕の費用を把握するには、長期修繕計画が必要です。ご自分でガイドラインに沿ったものを作ることもできますが、不動産管理のプロである、不動産管理会社に依頼をして、長期修繕計画と建物管理を同時にお任せする方が、相談をしながらすすめられそうです。まずは、複数の管理プランを比較して、大規模修繕に実績のある不動産管理会社を探してみてください。
賃貸経営・土地活用の
相談をしたい方はこちら
複数の会社にまとめて相談