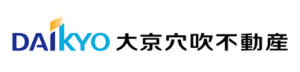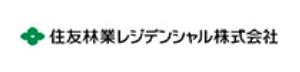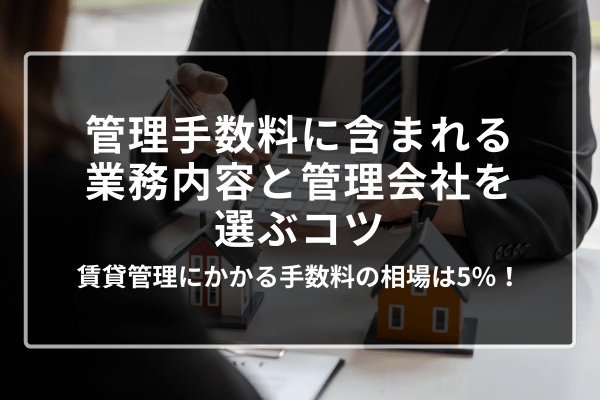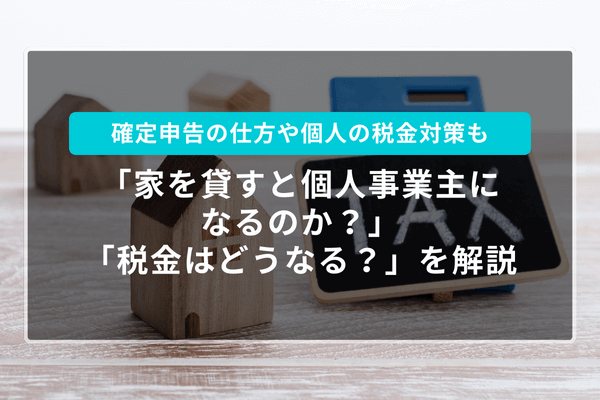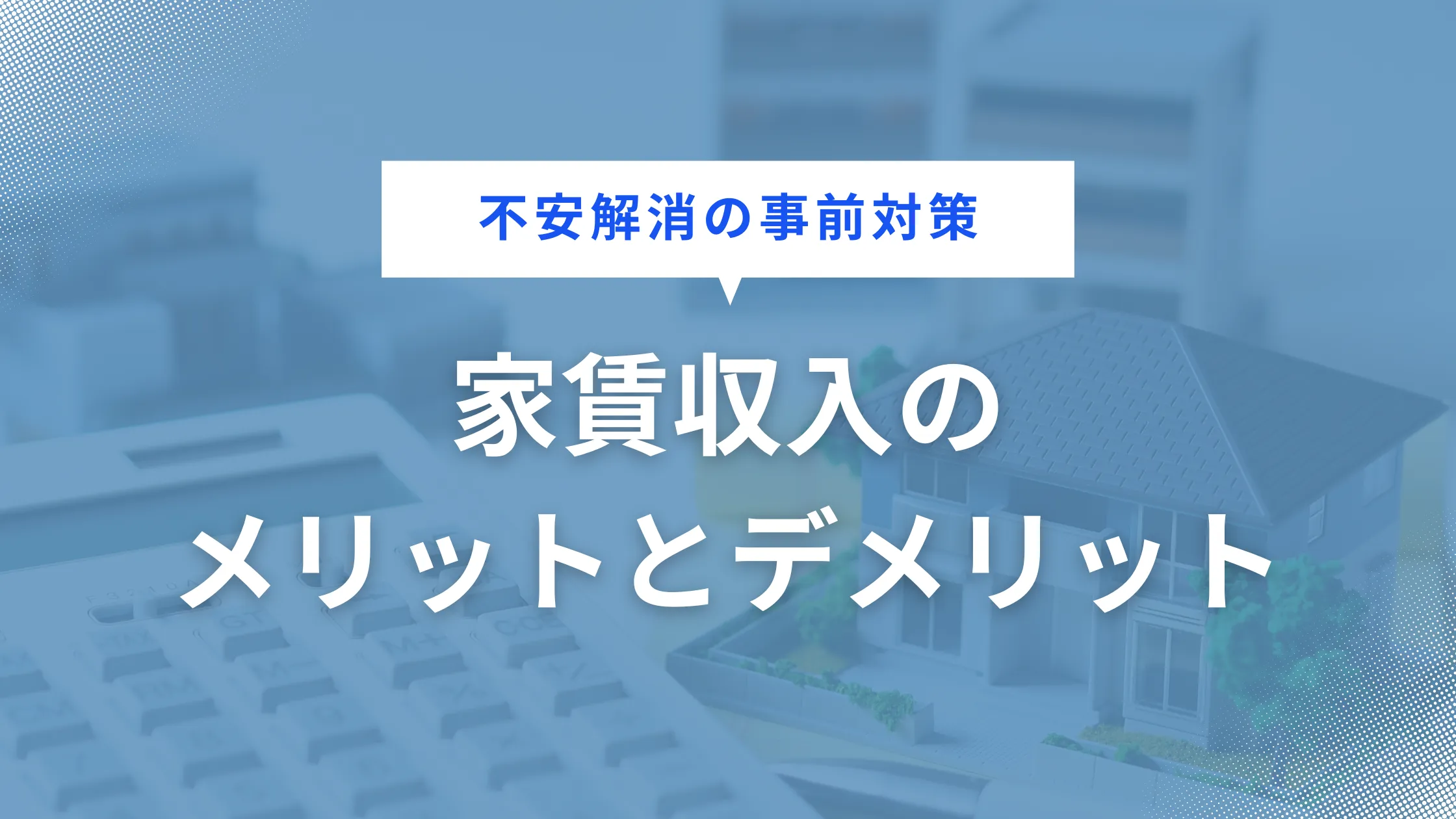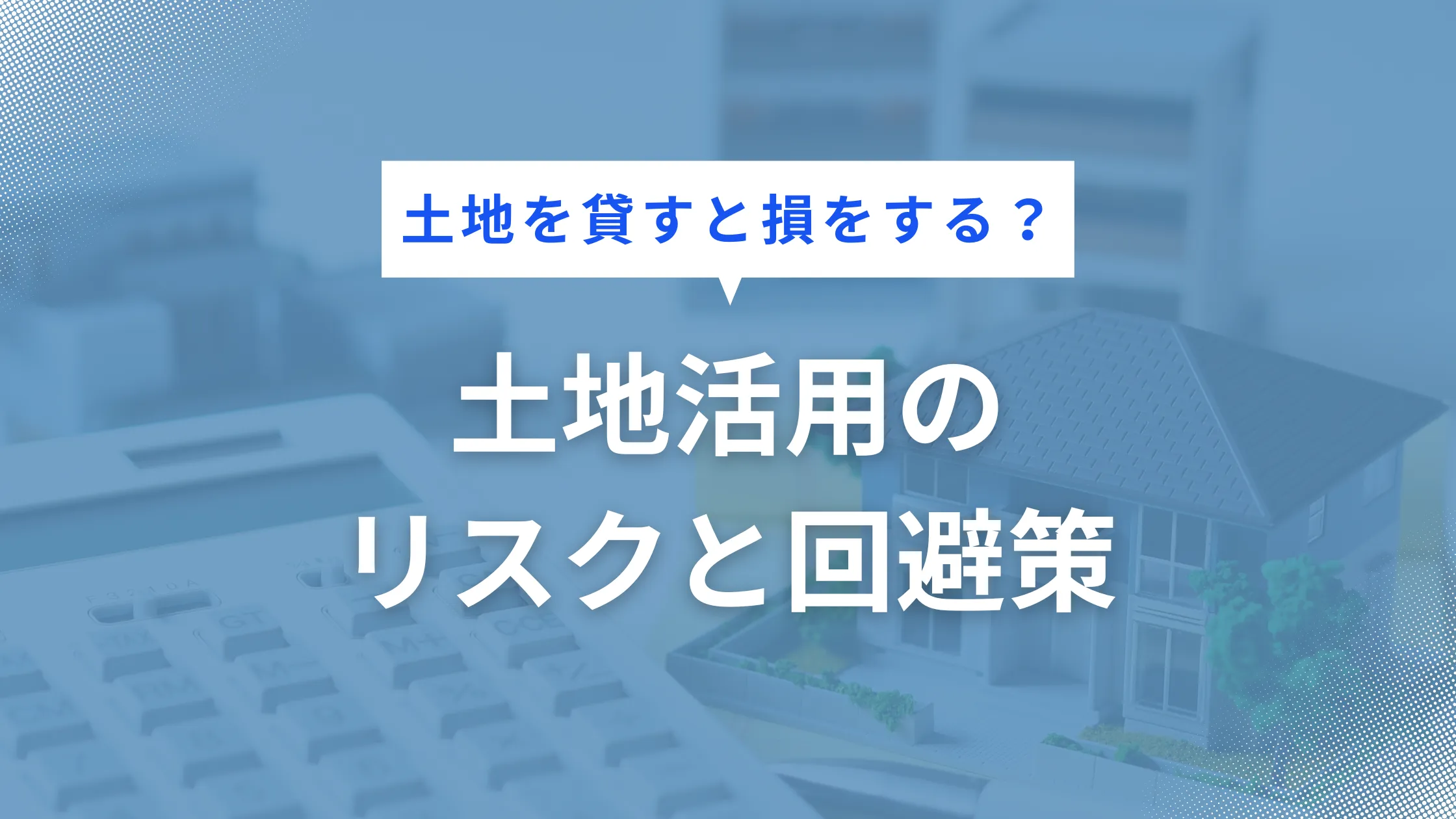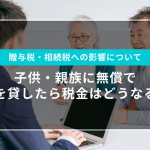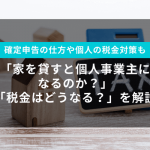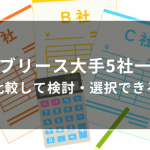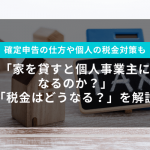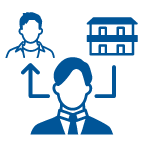マンション貸すと税金かかるって本当?はじめての不動産賃貸の税金・確定申告・節税
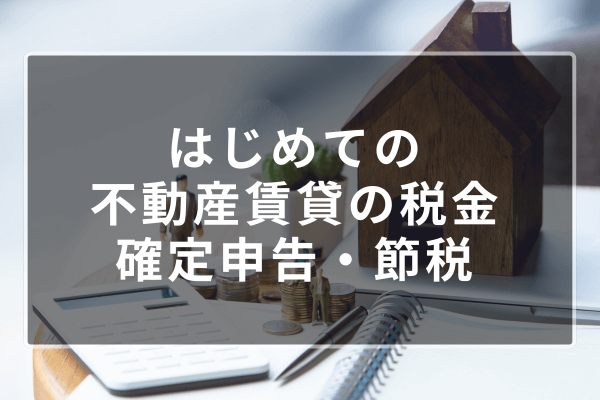
所有していたマンションを人に貸して、賃料収入を得ようとご検討中の方は、収入が増えることによって税金も増えるのではないかと、不安になりますね。賃料収入から必要経費を引いて20万円以上の利益があれば、確定申告をする必要が出てきます。今回は、はじめての賃貸経営で発生する税金に関して、全体的なイメージがつかめるように説明しています。

この記事の内容
1.マンションを貸すとかかる税金のはなし
ご所有のマンションを賃貸に出すと、賃料収入が発生して、賃貸経営が始まります。もともと持っていた物件ですので、人に貸す前から支払っている税金と、人に貸したことによって、新しく発生する税金とがあります。どちらも支払い義務があります。
- 所有マンションを貸すと新たに発生する税金
- 今までと同じに支払う税金
1-1.所有マンションを貸すと新たに発生する税金
不動産を人に貸して賃料収入を得ることによって、新たに発生する税金は、以下の3つです。経営状態や貸し方などによって発生する・しないものがあります。
- 不動産所得税(ほぼ発生する)
マンションを人に貸すと家賃収入が発生します。1年間の家賃収入合計から、必要経費を差し引いた金額を不動産所得といい、年間20万円以上の不動産所得がある場合は、所得税の支払い義務が生じます。
- 事業税(ケースによる)
事業税とは、事業を営んでいる法人・個人が負担する税金です。個人事業税の税率は5%、年間所得が290万円を超えている場合、個人事業税の対象になることがあります。
ただし、個人事業税はマンション経営を「事業」として営んでいる個人を対象としているため、年間所得が290万円を超えていても、課税対象外になることもあります。自治体によって判断方法に違いがありますが、一般的には、個人で経営するマンションが5棟以上、または10室以上ある規模を事業と呼んでいます。それ以下の規模の場合は、事業税の対象にならない可能性が高いと言えます。
- 消費税(ケースによる)
ご所有のマンションを「住居」として貸している場合は、消費税はかかりません。しかし、賃貸物件が店舗・テナントなど、人が住むことを前提としていない物件の場合は、消費税が発生しますので、確定申告と合わせて消費税の申告も必要になります。消費税の申告にはインボイス制度への事前登録が必要です。
【参照:国税庁 インボイス制度について】
所有していたマンションを人に貸すと、発生する税金についてまとめました。もともと支払っていた税金に、賃料収入が入ることによって、新しく不動産所得税が追加されることがわかりました。所得が増えたら確定申告をする必要がありますので、帳票や領収書をしっかり整理して、健全経営ができるようにしてください。これからの賃貸経営を検討中の方は、まずは、どのような経営方法があるのかを、賃貸経営プランの一括請求で確かめてみてください。
1-2.今までと同じに支払う税金
賃貸経営をはじめる前から、マンションを所有することで支払っていた税金です。これからも、引き続き、支払う必要があります。
- 所有不動産の固定資産税 都市計画税
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産(土地建物)を所有する方に課せられる地方税です。都市計画税は、市街化調整区域内に物件がある方に、固定資産税と一緒に課税されています。マンションをお持ちの方は、今までも支払いをしてきています。
固定資産税額は、毎年6月頃に物件がある自治体から郵送されてきます。賃貸物件以外にマイホームなどをお持ちの方は、それぞれの物件がある地方自治体から、固定資産税の支払い通知が来ます。
- 会社員給与などの所得税・住民税
会社員・パート・アルバイトなどで給与所得がある方は、所得税と住民税を支払ってきています。この税金は、源泉徴収という給与から天引きされる形で支払っていますので、ご自分では申告をしていません。気になる方は、給与明細を確認し「源泉徴収」という項目を確認してください。
不動産所得が増えても、今までの給与収入からの天引きには変更がありません。ただし、不動産所得の確定申告をすることによって、所得税・住民税とも節税※できることがあります。
住民税は、所得税に連動して自動計算され、住民税決定通知書は毎年5月から6月にかけて市区町村から送付されます。納付方法はご自分で納める方法と、給与天引きされる方法の2つがあります。ご自分で納める場合は、住民税決定通知書に支払い用紙が同封されています。
【参照:※国税庁 損益通算】
マンションを賃貸に出すことで、ご自分に関わりのある税金が、おおまかに理解できたと思います。この中で、ご自分で計算などをするのは、不動産所得だけです。給与所得は会社で計算をしてくれますし、固定資産税などは自治体が計算したものが郵送されてきます。
会社員の方は、マンションを人に貸すことによって、ご自分で確定申告をする必要があるため、はじめてのことで不安も多いかと思います。慣れないうちは、税金の計算方法などもふくめて、親身なアドバイスをしてくれる不動産会社の存在が大きいと言えます。
NTTデータグループが運営する「賃貸経営HOME4U」の一括プラン請求では、はじめてのマンション賃貸経営でも、スムーズにスタートできるように、適切なアドバイスができる信頼と実績の高い不動産会社が多数、提携しています。ご所有のマンションを貸そうとご検討であれば、まずは、頼りになる相談先として、不動産会社探しからはじめてみてください。
賃貸経営・土地活用の
相談をしたい方はこちら
複数の会社にまとめて相談
2.マンションを貸したときの税金の計算方法
マンションを貸した場合の、税金の計算方法をかんたんに説明します。税額算定のもとになる不動産所得は、以下の計算式に当てはめます。
「不動産所得 = A家賃収入 ー B必要経費」
主に、確定申告の時に使いますが、今はスマホやパソコンから国税庁の申告ソフトが自動計算をしてくれますので、ご自分で計算する必要はありません。本章では、上記計算式に、不動産経営で扱うお金の、何を当てはめていくのかを理解していきます。
- A:家賃収入に含まれるもの
- B:必要経費になるもの
- 100万円で税金シミュレーション計算
2-1.A:家賃収入に含まれるもの
家賃収入に含まれるものは、次のものです。不動産を貸すことによって入って来るお金ですので、敷金や保証金など、退去時に返還するものは収入になりません。
- 家賃収入
- 駐車場代
- 礼金(礼金がある地域のみ)
- 更新手数料
- 住人から徴収する管理費や共益費
2-2.B:要経費になるもの
マンション経営のためにかかる費用は、必要経費として不動産所得から差し引かれます。必要経費には、以下のようなものがあります。
- 不動産を所有することで発生する税金
・不動産取得税:購入・贈与などで不動産をあらたに取得した場合
・登録免許税:相続・購入・贈与などで名義登録・名義変更をする場合
・固定資産税:不動産所有者に課せられる地方税 - 物件の維持管理費
修繕費・設備の備品購入・美化清掃費・リフォーム費・原状回復費のオーナー負担分 - 損害保険料
火災保険・地震保険の代金 - 不動産管理会社への業務委託費
- 不動産会社への仲介手数料・インセンティブ費
- 減価償却費
- ローン利息
- 修理修繕費
- マンション経営のために使った交通費
- マンション経営のための資料・情報など
書籍・ソフト・DVD・セミナー参加費・懇親会費など
2-3.100万円で計算シミュレーション
マンションを貸した場合、税金計算はどうなるのか、年間賃料収入100万円でかんたんシミュレーションしてみました。実際の計算は、国税庁のソフトやスマホアプリなどで自動計算※しますので、ご自身で計算する必要はありません。計算に必要なのは、年間収入と必要経費に関した情報のみになります。
※国税庁のソフトやアプリは試算にも使えます。提出しない限り税額決定にはなりませんので、なんどでもやり直せます。
まずは、収入が賃料収入だけのケースです。
【例1:年収が賃料収入のみのケース】
| 賃料収入 | 100万円 | マンションの賃料収入1年分 |
|---|---|---|
| 必要経費 | 60万円 | マンションの経営に必要な経費1年分 |
| 不動産所得 | 40万円 | 100万円-60万円=40万円 所得税の課税対象となる金額 |
| 所得税基礎控除 | 48万円 | |
賃料収入から必要経費を差し引いた、不動産所得は40万円です。年間所得が20万円を超えるので、所得税の課税対象ですが、所得税の基礎控除額が48万円であるため不動産所得額は0円となり、このケースでは、所得税は発生しません。
次に、独身の会社員の方が、副業としてマンション経営を始めたケースを計算してみます。
【例2:会社員の給与収入500万円+マンションの賃貸収入を得るケース】
| 賃料収入 | 100万円 | マンションの賃料収入1年分 |
|---|---|---|
| 必要経費 | 60万円 | マンションの経営に必要な経費 1年分 |
| 不動産所得 | 40万円 | 100万円-60万円=40万円 所得税の課税対象となる金額 |
| 年収500万円 | 手取り356万円 | 源泉徴収済 所得控除:収入金額×20%+44万円=144万円 |
| 所得税基礎控除 | 48万円 | |
| 保険料等控除 | 30万円想定 | |
所得(給与手取り356万円+不動産所得40万円)-(所得税基礎控除48万+保険料等控除30万円)=318万円が、所得税の課税対象額になります。
所得税率は195万円 ~330万円以下までは10%、税額控除は97,500円ですので、(318万×10%=318,000円)-97,500円=220,500円が、支払うべき所得税額になります。会社で源泉徴収をされている方は差引した金額のみを納付します。支払い過ぎている場合は還付されます。
3.マンションを貸すときの確定申告に関した7ポイント
マンションの賃料収入から、必要経費を差し引いた手残りが20万円を超えていれば、確定申告の必要が出てきます。実際の支払い税額がいくらになるのかは、確定申告の計算をしてみないとわかりません。確定申告の計算には、年間賃料収入、1年間に支払った経費の総額、保険料などの総額、その他の控除額などの情報が必要ですので、スタート前の段階では、ハッキリした数字は出しにくいと言えます。
そこで本章では、マンション賃貸経営をスタートする前の段階で、確定申告に関して理解しておくべきポイントを7つにまとめています。
- 年間所得が20万円以上あれば確定申告が必要
- 赤字でも確定申告をした方が良い時がある
- 青色申告・白色申告は戸数・規模で決まる
- 賃貸経営をはじめた翌年に申告をする
- 申告に必要なのは領収証と帳簿
- 今はスマホでも確定申告ができる
- わからなければ無料の税務相談ができる
3-1. 年間所得が20万円以上あれば確定申告が必要
確定申告の必要性は、年間賃料収入から必要経費を差し引いた金額(不動産所得)が20万円以上ある場合です。20万円以下の場合は、収入があっても確定申告をする必要はありません。
この20万円は不動産所得に関したことであり、他の収入がある方は、すべてを合算したうえで経費を差し引き、必要な場合は確定申告をする必要があります。他の収入とは、利子所得・配当所得・事業所得・給与所得・退職金・山林所得・譲渡所得・公的年金・非営業用貸金の利子・副業所得などのことです。
3-2.赤字でも確定申告をした方が良い時がある
年度によっては、賃料収入から必要経費を差し引いた金額が、赤字になることがあります。不動産所得が20万以下ですから確定申告の必要性はないのですが、赤字でも確定申告をした方が良い時があります。
たとえば、会社員として給与所得を得ている方は、不動産所得が赤字でも、損益通算をすることで、会社員として支払った税金が還付されるケースがあります。損益通算とは、給与所得に不動産の赤字をぶつけて相殺する税金の計算方法です。赤字をぶつけることで、個人の年収総額が下がりますので、税率や税額が下がることがあります。
3-3.1物件だけなら白色申告でOK
確定申告には青色申告と白色申告とがあります。青色申告には、最大65万円の特別控除があるため、同じ不動産収入であれば、青色の方が所得税・住民税ともに節税効果が高くなります。白色申告は青色のような特別控除はありませんが、基礎控除として48万円があります。
青色申告を希望する方は、申告をする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請手続」を申請し、受理されている必要があります。申請は誰でもできますが、青色申告は事業性の高い収入に対して適用されますので、受理されないケースもあります。めやすは、区分マンションであれば10室以上、マンション棟であれば5棟以上の規模を、事業性があるとみなす傾向があります。
青色申告にすると、複式帳簿で記録をする必要があり、経理などの知識がない場合は、確定申告のための帳簿を外部委託する必要があるなど、お金と手間暇がかかるため、賃貸物件が少ないうちは白色申告で問題が無いと言えます。
3-4.賃貸経営をはじめた翌年に申告をする
確定申告は、マンション賃貸を始めた年の年末までの所得を、翌年度の3月15日までに申告・納付します。例えば、令和6年の7月にスタートした場合は、令和6年の7月1日~12月31日までの賃料収入合計から、必要経費を差し引いた金額に対し、令和7年3月15日までに確定申告をします。
経営期間によっては、不動産収入から必要経費を差し引いた金額が20万円以下になることがありますが、その場合は、確定申告の必要はありません。
3-5.申告に必要なのは領収証とカンタンな帳簿
確定申告で必要なのは、賃料収入の証明ができるものと、必要経費の証明ができるものです。賃料収入は不動産管理会社に委託管理をしている場合は、年末に収支報告書が郵送されますので、それをもとに記載をしていきます。自主管理の場合は、記帳をしたものをエクセルなどでつけていけば問題ありません。
必要経費の証明は、おもにレシートと領収証です。レシートがない場合は、手書きの記載や、スマホで価格と日時がわかる画像も使えます。控除証明が必要なもの以外は、確定申告書に添付するわけではないので、ご自分がわかるように整理してあればよいと言えます。
ただし、青色申告の場合は、複式簿記での記録が必要になります。複式簿記は、ひとつの取引に関して、借方・貸方(お金の入出金と、その原因)から取引内容を記録していく記録方法です。最後に必ず帳尻が合わなければならず、中級以上の簿記の知識が必要になります。
添付する帳簿書類にミスがあると、申告書類のやり直しや、税務調査が入ることもありますので、注意が必要です。複式帳簿作成に関しては、青色申告会などに加入をして申告相談や指南を受けるか、任意の税理士に申告書を作成してもらう必要が出てきます。
【参照:国税庁 青色申告制度】
3-6.今はスマホでスマートに確定申告ができる
確定申告の書類作成は、令和6年(2024年)よりスマートフォンからも作成できるようになりました。もともと、パソコン版の確定申告書等作成コーナーがあり、それをスマートフォンからも操作できます。

【参照:確定申告書等作成コーナーのスマホ画像】
上記のような画面が出てきますので、案内に沿ってご自分の情報や金額などを入力していくと、所得金額や税額が自動計算されます。所得税以外にも、消費税や贈与税の申告書作成、青色申告の決算書作成など、申請のための書類を正確に作成できます。
作成途中でも保存をして、やり直しが何度でもできますので、はじめてでも失敗なく書類作成ができます。作成した申告書データは、印刷不要で、スマートフォンからそのままe-Tax送信できます。同じものはパソコンからも作成できます。申請書への手書きでも構いませんが、計算間違いなどを避けるためには、なるべく国税庁の確定申告等作成コーナーを利用してください。
所得税の納付方法は、振替・電子納税・クレジットカード納付・コンビニ納付・現金納付・スマホアプリ納付から選択できます。
3-7.わからなければ無料で税務相談ができる
はじめての確定申告に関してわからないことがある場合は、毎年1月~3月の間に、所轄の税務署で無料の税務相談会が行われています。書類作成の不安以外にも、帳票類の仕分けが合っているかなどを、専門家に直接確認することができます。また、対面以外にも、電話相談も受け付けています。かんたんな確認事項であれば、国税庁のチャットボットで質問をすれば、回答を得られます。
【参照:国税庁 税についての相談窓口】
ご所有のマンションを貸して賃料収入を得ようとご検討中の方は、まずは、賃料収入がいくらくらいになるのか、必要な経費はどのくらいかかるのかなどを、不動産のプロフェッショナルに相談するところからスタートしてください。
NTTデータグループが運営する「賃貸経営HOME4U」の一括プラン請求では、一度の記入でたくさんの不動産会社へとプラン請求ができますので、賃貸経営プランを一度に比較できます。複数のプランを比較していくことで、ご所有のマンションの想定家賃、運営のための経費などが概算でわかるようになり、税金の予想もしやすくなります。
4.マンションを貸すと使える節税方法
ご所有のマンションを賃貸に出すことによって、次のような3つの節税ができます。どの方法も、多くの不動産投資家・不動産オーナーが採用している方法です。
- 減価償却による節税
- 損益通算による節税
- 相続税の節税
4-1.減価償却による節税
マンション経営の記事をネットで追っていくと、かならず出てくるのが減価償却に関したものです。減価償却をかんたんに説明すると、値段が大きくて長期間使えるものは一度に全額を経費にせず、一定の期間にわたって分割して計上しましょうという、会計上の考え方です。
減価償却費は会計上の経費支出であり、実際の出費を伴わないので、減価償却費が大きければ、その分、経費が増えて課税対象額が減り、所得税を減らすことができます。
鉄筋コンクリート造マンションの法定耐用年数は47年ですので、新築の場合は、マンション価格を47年で割った金額が、毎年の節税額になります。ご所有のマンションを貸し出す場合は、ある程度の使用期間があった後に貸し出しますので、築25年目で銀行査定額が5,400万円のケースを例に、かんたんなシミュレーション計算をしてみます。
減価償却期間の計算方法は「(法定耐用年数-使用期間)+(経過年数×20%)」です。やり方や計算方法を覚えるのではなく、このように計算をするのだなという、税額のイメージをつかんでください。
法定耐用年数47年 鉄筋コンクリート造マンション
貸し出す予定のマンション 築25年目減価償却期間の計算 (47年-25年=22年)+(25年×20%=5年)=27年
毎年の減価償却費 5,400万÷27年=200万円
上記のように、不動産収入から、毎年200万円を27年間にわたって経費として減価償却できることがわかります。仮に、毎年の賃料収入が400万円あった場合、減価償却費を200万円計上しますので、会計上の賃料収入は200万円ということになります。しかし実際には支出をしていませんので、手元には現金が大きく残ることになります。
ただし、ご自分で住んでいた期間が長く、マンションの築年が古くなることによって、マンションの現時点での想定価格は変わります。築年の古いマンションの場合は、減価償却による節税は大きくは期待できないと言えます。
4-2.損益通算による節税
損益通算とは、不動産経営の赤字を、その他の収入にぶつけて赤字を相殺する、税金の計算方法です。個人の所得総額が減ることによって税額が減ることに加え、所得額によっても税率・控除額が変わることがあるため、大きく税負担を減らすことも可能です。以下は、所得額が変わることにより、税率がどう変わるかを記した表です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | |
|---|---|---|---|
| A | 1,000円 ~1,949,000円 | 5% | 0円 |
| B | 1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| C | 3,300,000C20%円 ~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| D | 6,950,000円 ~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| E | 9,000,000円 ~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| F | 18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| G | 40,000,000円 ~ | 45% | 4,796,000円 |
【参照:国税庁 所得税率】
マンション賃貸の水回りリフォームなどで、年500万円の赤字が発生した場合を例に、損益通算のシミュレーションしてみます。
- 本業のサラリーマン給与収入 1,000万円(表Eの税率33%)
- マンション賃貸の赤字 △500万円
- 損益通算 給与収入1,000万円-赤字500万円=年間所得500万円(表Cの税率20%)
- 本業の給与所得による税額想定 (1,000万円×33%=330万)-1,536,000円=1,764,000円
- 損益通算による税額想定 (500万円×20%=100万)-427,500円=572,500円
上記のように、損益通算によって所得総額が減る以外にも、赤字によって所得が大きく下がることにより、税率が33%→20%と1割以上も変わります。このように、損益通算には大きな節税効果がありますが、赤字を出すことが目的ではなく、適切なタイミングで経費を大きくかけることにより、税負担を軽くする方法であることに、注意をしてください。
4-3.相続税の節税
ご自宅として使っていたマンションを人に貸しておくと、相続税対策になります。人に貸している住居は、マンションの1室であっても「貸家」の扱いになります。相続において人に貸している家は、相続を受ける方が自由には使えないため、その不自由さの分だけ評価を割り引くという考え方があります。
計算方法は、次のように計算をします。建物については建物(マンションの部屋)の評価額に借家権割合(全国一律30%)を控除しますので、建物評価額を70%で評価します。土地については、マンション敷地全体の評価額を算出し、そこから1室分の敷地権割合(土地の持ち分割合)を計算します。建物と土地の価格を足したものが、相続税評価額の対象です。この計算方法は、戸建でも同じように算出します。
ただし、これらの制度が適用されるには、相続が開始される3年以上前から不賃貸業を行っていた場合のみが対象になります。
5.マンションを貸す前に準備しておくこと
マンションを貸す前に準備しておいた方が良いことを、5つにまとめています。ご自分が住んでいたマンションや、相続などで引き継いだマンションの1室は、人が住んでいた状態からのスタートあるため、家財道具の処分や、経年劣化による修理修繕の必要性があります。
賃貸物件となると、賃料を取る価値のある状態にしておかなければなりません。最低でも、室内の家財道具の処分と清掃は必要です。そのうえで、マンション経営をどうするのかを考える必要があります。
- 収支シミュレーションをしてから考える
- 火災保険の内容を確認する
- 住宅ローンの残債を確認する
- 必要な修理修繕などはしておく
- 頼りになる不動産管理会社を探しておく
5-1.収支シミュレーションをしてから考える
マンションを貸したら収支がどうなるのかを、シミュレーションしてみてください。単純にマンションを貸したらいくらになるかが知りたければ、「家賃収入-必要経費」で十分です。
毎月の収入10万であれば、1年で120万、ローン返済0円、必要経費を年間家賃の2割で考えて24万円と計算すれば、年間96万円が利益になります。
さらに不動産投資としての価値を知りたいのであれば、利回りを使ったシミュレーションも参考にできます。利回りとは、マンションを貸したときに、1年でどのくらいの利益を出せるのかを表す数字です。以下のように、試算をしてみました。
| 表面利回り(ざっくりとした利回り)=(年間収入)÷マンション価格×100 実質利回り(リアルな利回り)=(年間収入-必要経費)÷マンション価格×100 賃貸経営による年間経費 120万円×20%=24万円 想定現在のマンション価格 路線価による算出 3,000万円想定 想定空室率 1室しかないので、満室経営と想定します。 自己資金額 100万円 風呂トイレリフォーム代50万円 A表面利回り (年間収入120万)÷マンション価格3,000万×100=4% B実質利回り リフォームなし (年間収入120万-必要経費24万=96万)÷マンション価格3,000万×100=3.2% C実質利回り リフォームあり (年間収入120万-必要経費24万-リフォーム50万=46万)÷マンション価格3,000万×100=1.5% |
マンションの現在価格が投資額に相当しますので、ご所有のマンションの投資価値を見るのに役立ちます。上記例の場合、A表面利回りは4%、Bリフォーム無しの実質利回りは3.2%、Cリフォームありの場合は1.5%になりました。
Cのように、貸すための準備として手を加えると、その年の利回りは落ちます。しかし、翌年度からはリフォームやリノベーションの経費が発生しませんので、Bの利回りに戻ります。そのため、長い賃貸経営には利回りが下がることもありますが、基本的にはBの利回りが維持できると考えます。
ネット上にある不動産投資物件はAの表面利回りで表記されていますので、同じような利回りの商品と比較するときに使います。また、不動産だけではなく、株式や投資信託などの金融商品も含め、同じような利回りの投資先を比較し、投資をすべきかどうかの判断基準として使います。
このように、マンションを貸したらいくら手元に入るのか、所有するマンションを貸すことが、果たして投資として正解なのかを、総合的考えて判断してください。
5-2.火災保険の内容を確認する
ご所有のマンションを人に貸す場合、今まで入っていた保険から、オーナーズ保険に切り替える必要があります。賃貸に出すようになると、入居者は家財保険に新規加入し、オーナーは物件内の構造と設備に関した保障のある保険をかける必要があります。
たとえば賃貸中に水漏れ事故が起きた場合、入居者の家財道具は入居者の保険がカバーしますが、水で被害を受けた天井や床などの構造部分に関しては、オーナー責任でもとに戻す必要があります。建物の共用部分に関しては、管理組合で加入していることが多いので、あわせて確認してください。
5-3.住宅ローンの残債を確認する
賃貸に出そうとしているマンションに、住宅ローンが残っている場合は、ローンを完済しないと賃貸に出すことができません。住宅ローンは「マイホームのためのローン」であり、投資物件のために融資している性質のお金ではないためです。
手持ち資金で完済ができない場合は、いったん、賃貸にすること先送りにします。そのうえで、ローンを不動産投資用のアパートローンに変更できないかなど、融資機関に相談をしてみてください。
5-4.必要な修理修繕などはしておく
きれいに使っていたとしても、賃貸マンションとして借り手がつく程度の修理修繕は必要になります。特に、トイレ・キッチン・バスなどの水回りが汚いと、他の要素が良くても入居に結びつかないことがありますので注意してください。
どの程度までの経費がかけられるか、修繕費を何年で回収するのかなど、何通りものシミュレーションをしてください。また、不動産会社の管理プランを請求すると、賃貸経営プランの中に、必要な修繕箇所のアドバイスなどが盛り込まれていますので、参考にしてください。
5-5.頼りになる不動産管理会社を探しておく
不動産管理会社は、入居者募集・案内・契約・賃料振込・督促・更新の案内など、賃貸経営に必要な業務をすべて代行してくれます。マンション賃貸に関したことを何でも相談できる、頼りになるパートナー会社としての、不動産会社選びも真剣にしてみてください。
NTTデータグループが運営する「賃貸経営HOME4U」の一括プラン請求であれば、一回の入力で最大10社にまで、一度にプラン請求ができます。入力された賃貸マンションの条件をもとに、今後の賃貸経営プランを作成して、さまざまな角度からのアドバイスがもらえます。
住んでいたマンション、相続や贈与などで引き継いだマンションを、人に貸そうかと検討しているのであれば、まずは、一括プラン請求でたくさんの経営プランを比較してみてください。
まとめ
所有していたマンションを人に貸すと、発生する税金についてまとめました。もともと支払っていた税金に、賃料収入が入ることによって、新しく不動産所得税が追加されることがわかりました。所得が増えたら確定申告をする必要がありますので、帳票や領収書をしっかり整理して、健全経営ができるようにしてください。これからの賃貸経営を検討中の方は、まずは、どのような経営方法があるのかを、賃貸経営プランの一括請求で確かめてみてください。