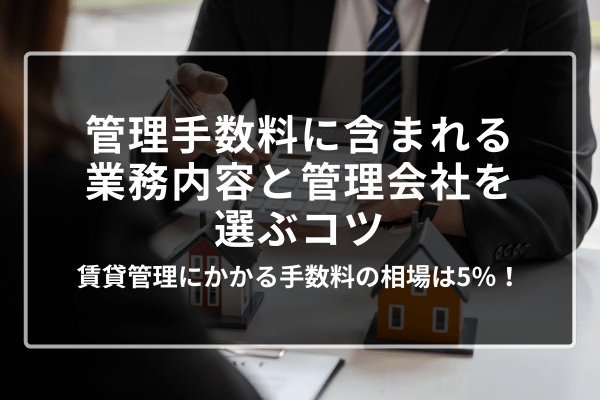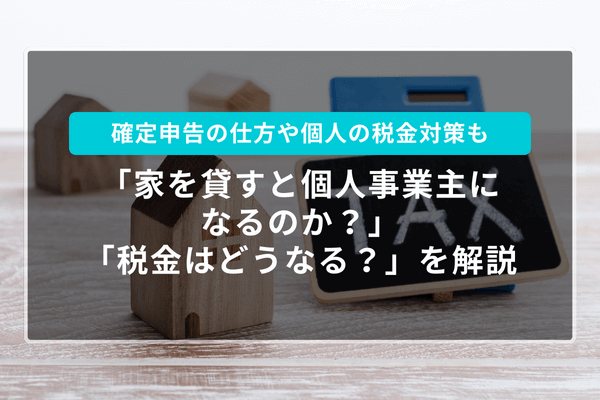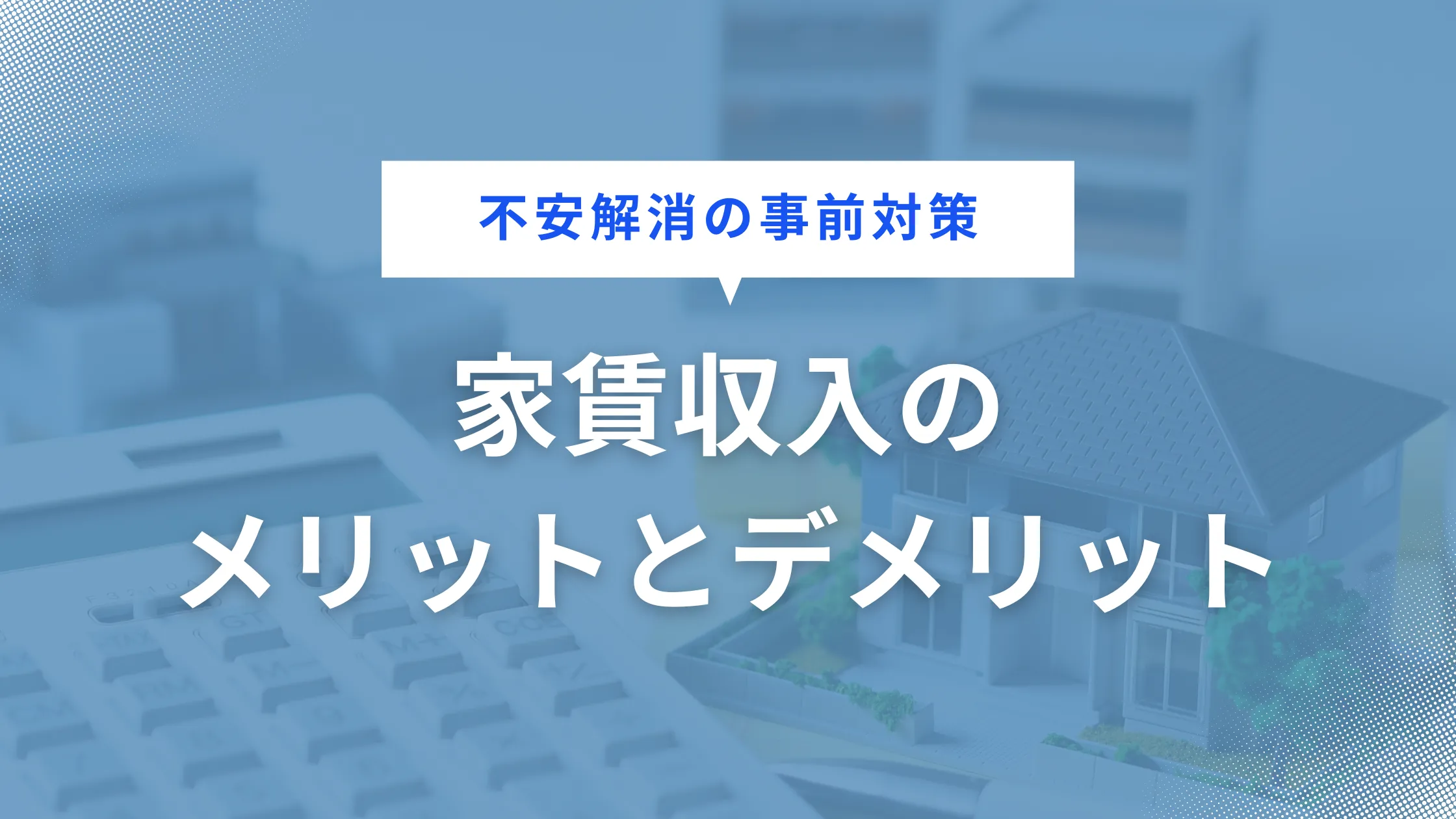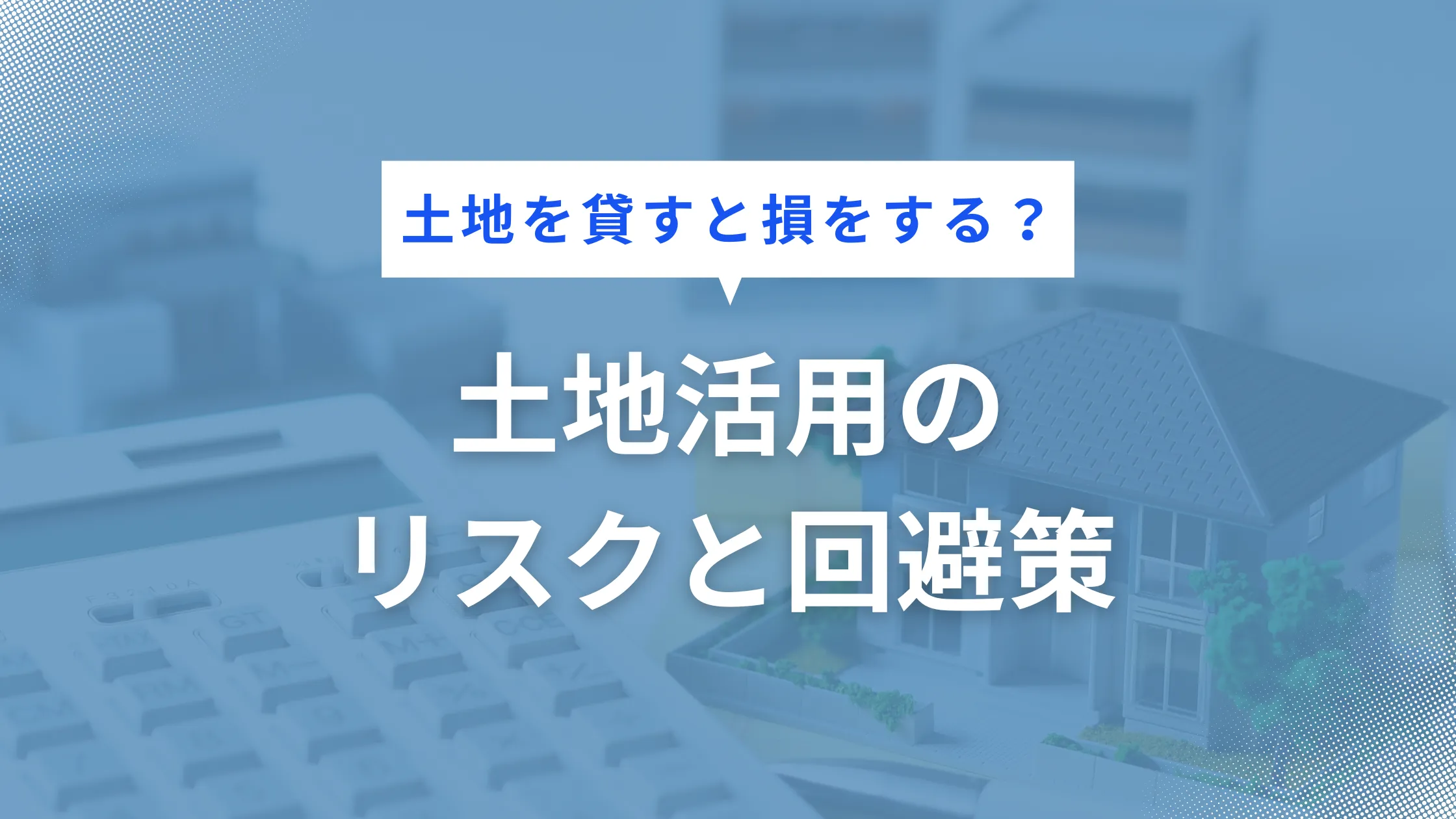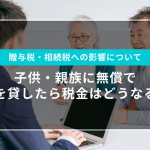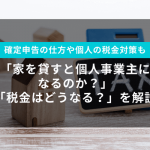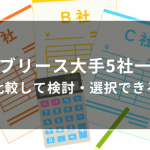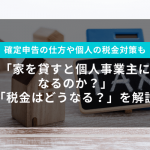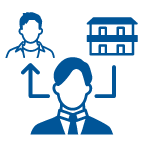子供・親族に無償で家を貸したら税金はどうなる?|贈与税・相続税への影響について

この記事では子供や親族に「無償で家を貸す」ことを検討している方向けに、「税金はどうなるのか?」についてできるだけ簡潔に解説し、なるべく損がない方法で「無償で家を貸す」事が実現するようにサポートしています。
実際、家を無償で貸すと税金の扱いが変わる場合があるため注意が必要です。
- 無償で貸す家は贈与税と相続税のどちらがお得か
- 親族に無償で家を貸した場合の「贈与税・相続税・固定資産税・所得税」の扱い
- 無償で家を貸すときの注意点
NTTデータグループが運営する「賃貸経営 HOME4U(ホームフォーユー)」なら、厳しい審査をくぐりぬけた約70社の中から、 最適な管理会社をシステムが自動で抽出し、無料で紹介!
この記事の内容
1.家を「子供・親族」に無償で貸すと税金はどうなる?
ずばり、
具体的な事例は以下のとおりです。
<家族間で家を貸す際の税金面の影響>
| 税目 | 種類 | 税金面の影響 |
|---|---|---|
| 贈与税 | 国税 | 無償貸与は原則贈与税の対象となるが、親子間は課税されないケースが多い |
| 相続税 | 国税 | 自用と判断されると、相続税評価額の減額なし |
| 固定資産税 | 地方税 | 無償でも有償でも影響なし |
| 所得税 | 国税 | 無償貸与の場合、諸費用経費に認められないため節税効果がない |
家族間での無償貸与は珍しくありませんが、「無償だから税金面に問題ない」とはいえないため注意が必要です。
2.無償で貸す場合は贈与税と相続税のどちらがお得?
家を無償で貸す場合、贈与税と相続税のどちらが有利かは状況によって異なります。
それぞれのメリットを理解し、自分の状況に合わせて選択することが大切です。
2-1.生前贈与が良いケース
〈生前贈与が良いケース〉
- 不動産価値の上昇が見込まれるケース
- 特定の相続人へ確実に財産を引き継ぎたいケース
- 将来、認知症などで判断能力の低下が心配されるケース
不動産価値の上昇が見込まれる場合、生前贈与のほうが贈与税等の税金面で有利になる可能性があります。
たとえば、再開発が予定されている地域の物件は将来的に価値が上がる確率が高いです。
上記のような場合、現在の評価額で贈与税を納付することで、将来の高額な相続税を回避できます。
また特定の相続人に確実に財産を引き継ぎたい場合や、認知症などで判断能力の低下が心配される場合も、贈与税等の税制面のメリットはないかもしれませんが相続時のトラブルを防げます。
参考:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
2-2.相続が良いケース
〈相続が良いケース〉
相続遺産の総額が基礎控除額より低い場合は、相続税がかかりません。
相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。
〈相続税の基礎控除額〉
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
また、不動産価値の低下が見込まれる場合も相続を選択するのがおすすめです。
相続税は相続時の評価額で計算されるため、価値が下がった時点で相続すれば税負担が軽くなります。
さらに、小規模宅地等の特例を適用したい場合も相続の方がお得で、相続税評価額を最大80%減額できる可能性があります。
参考:
国税庁|No.4155 相続税の税率
国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
3.親族に無償で家を貸した場合の贈与税の扱い
親族に無償で家を貸した場合、
ここでは、具体的な事例について解説します。
3-1.無償で家を貸すのは「使用貸借」
親族に無償で家を貸す行為は、法律上「使用貸借」と呼ばれます。
民法に定められた契約の一種であり、借主は無償で物を借りた後に返還を約束することが義務付けられています。
3-2.使用貸借は贈与税の課税対象か?
原則として使用貸借は無償の利益供与にあたるため、贈与税の課税対象となります。
しかし、親が子に家を無償で貸すのは「親の誠意によるもの」と考えられるため、実際は課税されないケースがほとんどです。
ただし、高額な家賃相当額を長期間にわたって無償提供するケースなど、親子関係を利用した租税の回避が疑われる場合は贈与税が課される可能性があるため注意してください。
また、贈与税には年間110万円までの基礎控除額(非課税枠)があり、使用貸借による経済的利益が年間110万円以内なら、贈与税は課税対象外です。
3-3.無償で貸す家のある土地を贈与する場合
他人に貸し出している土地を贈与する場合、自由な使用が制限されるため、土地の評価額が通常より低くなるケースが一般的です。
ただし、親族間の使用貸借ではいつでも土地の利用方法を相談できることから、減税の対象にならないケースがあります。
相続税の計算でわからないことがあれば、税務署へ事前に確認するのがよいでしょう。
4.親族に無償で家を貸した場合の相続税の扱い
親族に無償で家を貸している場合、
ここでは、具体的な計算方法を解説するので参考にしてください。
4-1.自宅以外の不動産の相続税計算方法
自宅以外の不動産、特に賃貸物件の相続税評価額は、通常の自用物件よりも低く設定されます。
賃借人が物件を占有しているために、所有者の自由な使用が制限されるためです。
賃貸中の建物(貸家)の評価額は、次の計算式で求められます。
〈貸家の評価額の計算式〉
土地については、貸家の敷地(貸家建付地)の計算方法は以下のとおりです。
〈貸家建付地の評価額の計算式〉
借地権割合は地域によって30~90%まで変動するため、国税庁の路線価図で確認してください。
4-2.親族に無償で家を貸している場合
親族に無償で家を貸している場合、所有者の自由な使用が制限されていない自用として評価されるため、減額措置は適用されません。また、いつでも返還を求められる状態にあるため一般の賃貸物件とは異なる扱いになります。
たとえば、10室あるアパートの1室を子供に無償で貸し、残り9室を他人に賃貸している場合は以下のように減額が適用されます。
〈親族に無償で家を貸した場合の相続税の扱い〉
安易に無償で親族に家を貸すと、かえって相続税が高くなることもあるので注意してください。
5.親族に無償で家を貸した場合の固定資産税の扱い
親族に無償で家を貸しても、
〈固定資産税の住宅用地特例〉
たとえば、300㎡の土地に建つ家を親族に無償で貸す場合の計算方法は以下のとおりです。
〈300㎡の土地の場合〉
ただし、アパートやマンションの場合は戸数分の面積が適用されるため注意してください。たとえば6戸のアパートなら、1,200㎡(200㎡×6戸)まで小規模住宅用地として扱われます。
また固定資産税の軽減だけでなく、都市計画税にも同様の特例が適用されるため、二重の恩恵を受けることが可能です。
6.親族に無償で家を貸した場合の所得税の扱い
親族に無償で家を貸した場合、
賃貸経営に関する支出は「家事関連費」とみなされ、事業のための支出ではないと判断されることから、減価償却費や固定資産税は経費として計上できません。
たとえば、10室あるアパートの1室を子供に無償で貸し、残り9室を一般に賃貸している場合は、子供に貸している1室分の経費は計上できないことになります。
ただし、子が借りた物件を事業目的で使用している場合は経費として計上可能です。
自分での判断が難しい場合は、税務署に相談してみるとよいでしょう。
7.無償で家を貸すときの注意点
家族や親族に無償で家を貸すときは、以下の点に注意してください。
〈無償で家を貸すときの注意点〉
- 契約書を作成する
- 贈与税や相続税が発生する可能性がある
- 親族間で貸す場合は借りない親族への配慮を行う
まずは無償貸与に関する契約書の作成をし、トラブルを未然に防ぎましょう。
契約書には貸借の目的や期間、返却のタイミング、破損時の対処法などを明記すると、将来の誤解や争いを防げます。貸主が亡くなっても使用貸借契約は継続しますが、借主が亡くなると契約は終了するため注意してください。
また、無償貸与は贈与税や相続税が発生する場合があります。通常の賃貸物件とは相続税評価額の計算方法が異なるため、節税にならないケースも多いです。
さらに、特定の親族だけに無償で家を貸すと、ほかの親族が不公平感を抱く可能性があります。
事前に家族全員の理解を得ておくなど、ほかの親族への配慮が大切です。
まとめ
子供や親族であっても、無償で家を貸すと贈与税・相続税・所得税・固定資産税といった各種税金にさまざまな影響があります。
自分にとって適切な判断が難しい場合は、税務署や信頼できる不動産会社に相談してみるのもおすすめです。
正しい知識を身につけて、後悔のない不動産経営を行いましょう。
この記事のまとめ
無償で家を貸す際は贈与税と相続税のどちらがお得?
無償で家を貸す際に贈与税と相続税のどちらが有利かは状況により異なります。
- 不動産価値の上昇が見込まれる場合、生前贈与が有利になる可能性がある
- 相続遺産の総額が基礎控除額より低い場合は、相続のほうが有利
詳細は「2.無償で貸す家は贈与税と相続税のどちらがお得?」にて解説しています。
親族に無償で家を貸した場合の相続税の扱いは?
親族に無償で家を貸した場合の相続税の扱いは以下のとおりです。
- 無償で家を貸すのは「使用貸借」となり、贈与税の課税対象
- 無償で貸す家のある土地を贈与する際は土地の評価額が低くなる可能性がある
詳細は「3.親族に無償で家を貸した場合の贈与税の扱い」にて解説しています。
無償で家を貸すときの注意点は?
無償で家を貸すときは以下の点に注意が必要です。
- 契約書を作成する
- 相続税が発生する可能性がある
- 親族間で貸す場合は借りない親族への配慮を行う
詳細は「7.無償で家を貸すときの注意点」にて解説しています。