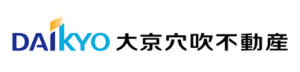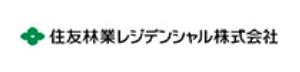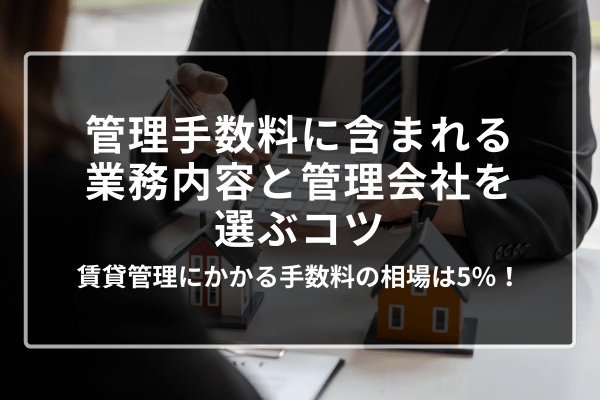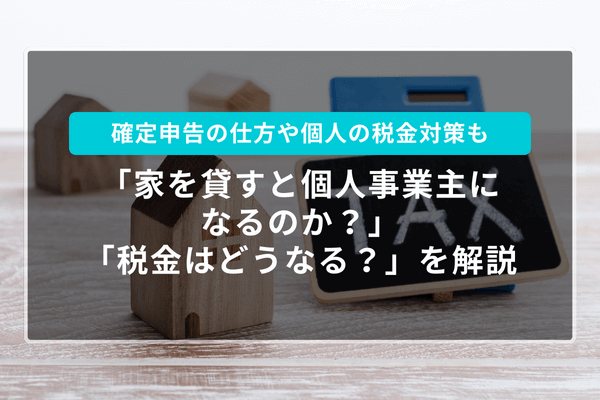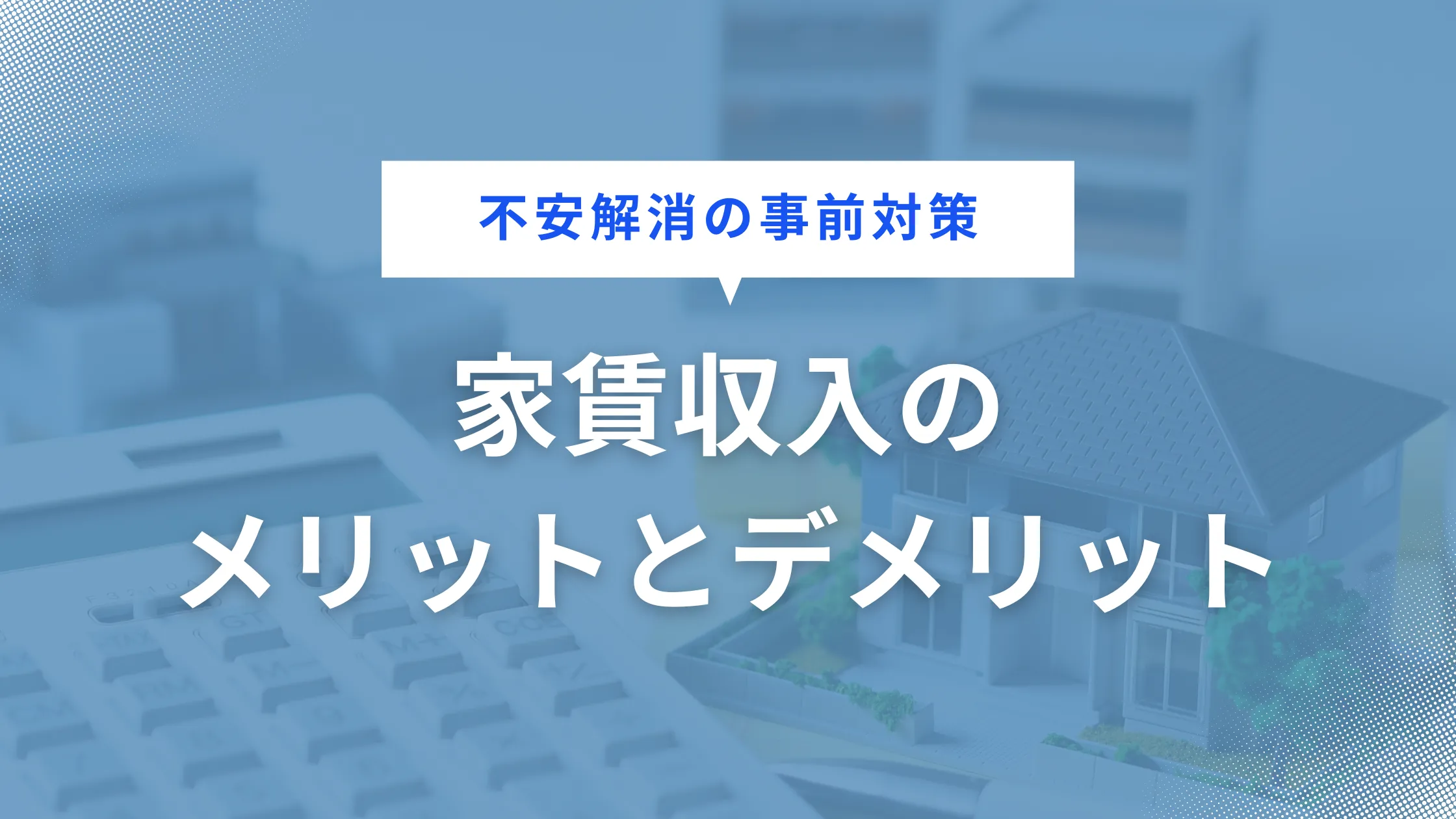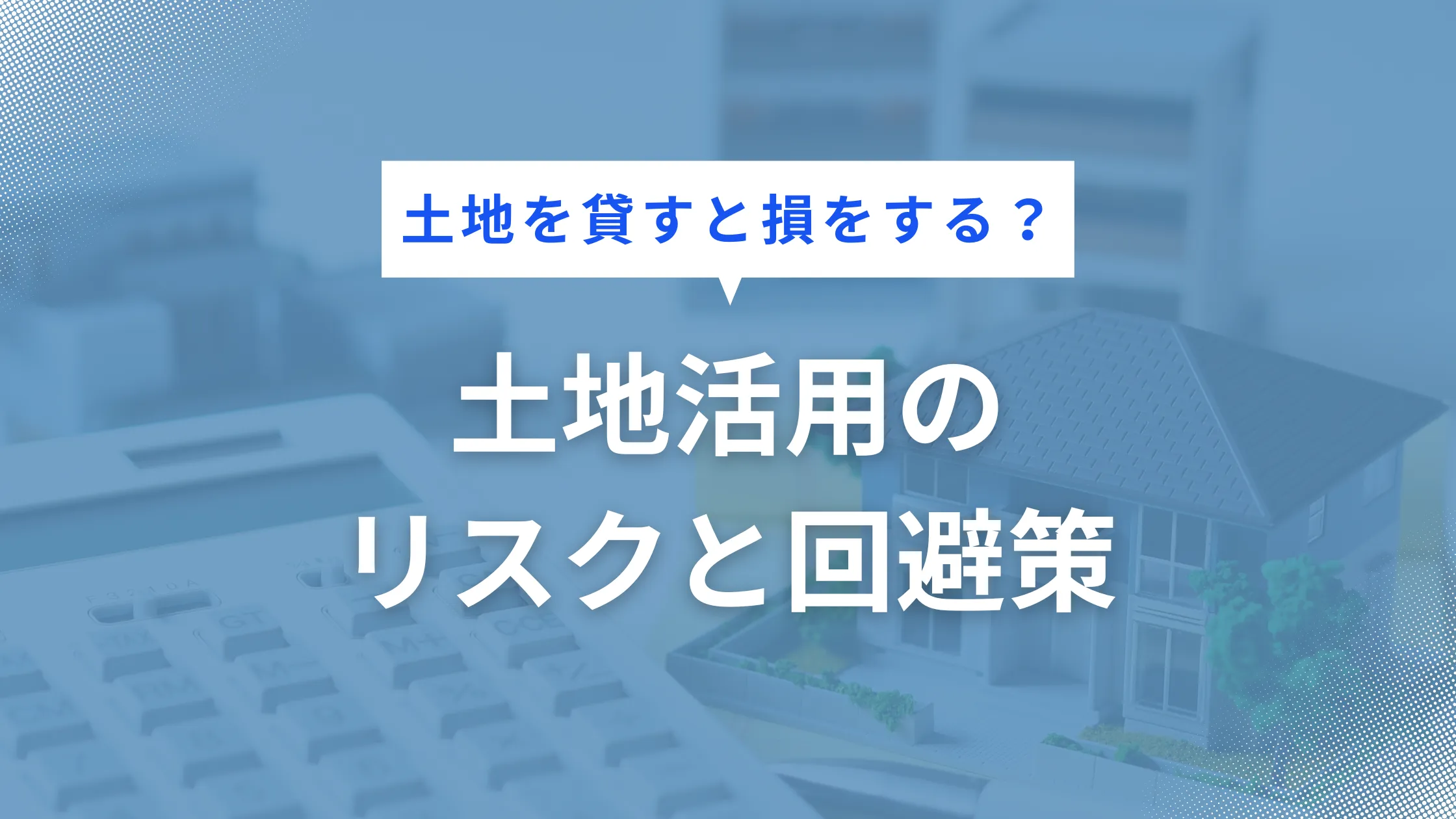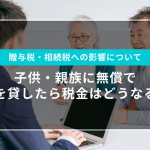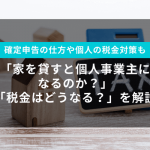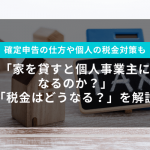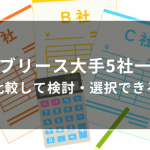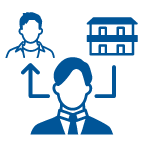空室対策でペット可物件にする5つのメリット・3つのデメリット

築年や設備が古くなってきた物件への空室対策として、ペット可物件は有効な選択肢です。しかし、既存入居者との関係性や、新しいルール作りなど、思った以上にオーナーが準備しておくことがあります。本記事では、ペット可物件にするメリットとデメリット、物件をペット可にするまでの流れを、10のステップにわけて、わかりやすく解説しています。

この記事の内容
1.空室対策としてペット可物件にする5つのメリット
空室がなかなか埋まらない状態が続いている場合は、空室対策として、ペット可物件にするという選択肢があります。ペット可物件にすると、賃貸経営をするうえで以下の5つのメリットがあります、
- 入居者の対象が広がる
- 賃料アップしやすくなる
- 長期更新が期待できる
- 土地条件の悪さもプラスになる
- 明確な差別化になる
1-1.入居者の対象が広がる
ペット可物件にすると、現在ペットを飼っている方と、これからペットを飼いたいと思っている方の両方が入居者対象になります。お部屋探しをする方の間口が広がりますので、内見申し込みも増えて、入居が決まりやすくなる可能性があります。
最近の分譲マンションはペットありきの物件が多いのですが、賃貸市場でのペット可はまだまだ少ないため、ペットが飼えるお部屋のニーズは高いと言えます。ただし、周辺エリアにすでに十分なペット可物件がある場合は、今からペット可にしても、空室対策の効果が期待できない可能性があります。
不動産管理会社に、空室対策としてペット可物件にしたいという相談をし、エリアマーケティングをしてもらってから、データをもとに判断するようにしてください。
1-2.賃料アップしやすくなる
ペットと一緒に住める賃貸物件は少ないので、ペット可物件にすると賃料アップが期待できます。ただし、ペット可物件としての周辺相場がありますので、良く調べたうえで賃料を決めてください。
比較の際には、周辺のペット可物件がそろえている設備や条件などもチェックしておき、ペットを飼っている方が「うちの子が暮らしやすそうだな」と思ってもらえる、賃料に見合ったお部屋づくりをしておく必要があります。
1-3.長期更新が期待できる
ペット可物件は賃貸市場全体から見ると少数ですので、お部屋探しは困難を極めます。そのため、入居が決まると長期更新につながりやすくなります。
ペットにとって、賃貸のお部屋は自分たちのなわばりですので、度重なる引越しは大きなストレスになります。飼い主はこのことを理解しているため、なるべくペットにとって安全に長く住めて、さらに自分にとっても住みやすいペット可物件を探しています。そして、そのような物件は多くはないので、良い物件を見つけたら、そこにずっと住んでいようという気持ちが働きます。
転勤などによるやむを得ない事情がない限り、飼い主はペットの住環境を優先しますので、長期更新につながりやすくなります。1-4.土地条件の悪さもプラスになる
駅から遠い、周辺にコンビニが少ないなど、一般的に賃貸経営に不利だと言われる土地条件でも、ペット可物件にすると好条件に変わる傾向があります。
たとえば、犬を飼っているのであれば、駅から遠くても、周辺に大きな公園や川などの自然が多いのは、毎日の散歩コースとして適しています。家から出ない猫やうさぎなどのペットでも、車のクラクションや繁華街の音がする場所よりも、鳥の声や自然の木々の音や香りがするエリアの方が、住環境としては適しています。
このようなペット可として良い条件は、子育ての環境としても良いため、乳幼児のいるファミリー層にも需要が広がる可能性があります。
1-5.明確な差別化になる
ペット可物件は、周辺のライバル物件との差別化ポイントになります。とくに、周辺にペット可物件が少なければ、賃貸経営としては大きなチャンスといえます。
ペット可物件を探す方は、不動産ポータルサイト(SUUMOなど)の詳細条件のところで、「ペット可」にチェックをいれて探します。そのため、検索の時点で、100%ペットありきでお部屋探しをしている方が対象になりますので、成約にもつながりやすくなります。
賃貸経営・土地活用の
相談をしたい方はこちら
複数の会社にまとめて相談
2.空室対策としてペット可物件にする3つのデメリット
物件をペット可にすると空室リスクが下がる代わりに、以下のような3つのデメリットが発生します。これらのデメリットは、事前対策が可能です。
- クレームが起きやすくなる
- 可能性入居者同士によるトラブルの可能性
- 原状回復リスクが上がる可能性
2-1.クレームが起きやすくなる可能性
空室対策でペット可物件にする場合、もともとの入居者は、ペットがいない前提で契約をしていますので、新たなクレームが発生する可能性が高くなります。
ペットを飼う習慣がない方にとって、動物のニオイ・鳴き声・足音は気になるものです。たとえば、犬であれば、飼い主がいる時間帯は静かにしていても、会社に行っている時間帯には、さみしさから吠え続けていることがあります。
小動物がソファから床へ飛び降りたときの音、多頭飼いの犬や猫が床を走り回る音なども、ペットを飼っていない人にとっては騒音です。最初は我慢をしてくれていても、毎日のことであればストレスになりますので、最終的にはクレームへと発展していきます。
対策>
普通の賃貸だった建物にペット可物件を追加する場合は、先に、入居者から理解と承諾を得ておく必要があります。既存の入居者の中に、1名でも反対者がいるとクレーム発生率が高くなりますので、その場合は、空室対策としてのペット可は先送りをしてください。
既存入居者の方々が動物好きであっても、アレルギーなどの健康被害が出る可能性もありますので、丁寧な聞き取りをしたうえで、慎重に検討してください。階数や物件数に余裕があれば、ペット可専用フロアや専用棟などを作り、ペットが苦手な方はオーナー負担で別の物件に移動してもらうなど、既存入居者への対策を検討しながら、空室対策としての費用対効果も計算しておく必要があります。
2-2.入居者同士によるトラブルの可能性
すべての方が動物好きなわけではありませんので、ペット可にしたことより、入居者同士のトラブルが起きやすくなります。特に、散歩のために外出をする犬の場合、どうしてもエレベーターや廊下などの共用部分で、他の入居者と遭遇する機会があります。
ペットオーナーにとっては当たり前の鳴き声・ニオイ・動きなども、動物が好きではない方にとっては、不快に感じることもあります。また、中には動物を怖いと感じる方もいらっしゃいます。
特に、空室対策によるペット可の場合、後から入ってきた方=ペット可ですので、物件に長く住んでいた方ほど、環境が変わって、嫌な思いをする可能性が高くなります。ストレスが高まれば入居者同士のトラブルに発展する可能性があります。
対策>
ペット可への同意が取れていることが前提で、飼育マナーと共用部分の使用ルールについて、オーナーと不動産管理会社で細則を決めます。もとから入居している方には、ルールができた時点でお知らせをし、内容に不備がないかを確認してもらい、承諾の署名をしてもらいます。
ルール作成前に、クレームが起きる可能性があることをリストし、適切な対応ができるように、不動産管理会社と話し合っておく必要があります。現在契約中の不動産会社に、ペット可物件の経験則が少ない場合は、経験と実績の多い不動産管理会社に変更することも検討してください。
2-3.原状回復リスクが上がる可能性
ペット可物件にすると、原状回復費が高くなる傾向があります。ペットの種類に関係なく、爪による細かな床面のキズ、壁のひっかき傷や齧ったあとなどは、必ず発生すると言ってよいでしょう。
しつけをキチンとしていても、飼い主が気付かないうちに、室内の隠れた場所にこっそりとマーキングをしていることもあります。それを長期に放置されてしまうと、構造の木材やコンクリートにニオイが染みついてしまうケースもあります。
対策>
ペット可物件は敷金を多めに徴収しているので、平均で賃料2~3か月分の準備費用があります。この金額でカバーできれば問題はないのですが、それ以上の金額になった場合は、オーナー負担になることもあります。
すべては、契約時の原状回復の細則で決まりますので、不動産管理会社と相談しながら、最悪のケースを想定した契約内容にしておく必要があります。経験の多い管理会社であれば、過去の事例をもとにして、必要なルールつくりをおまかせできます。
3.経営中の物件をペット可にするまでの10STEP
経営中の物件をペット可にするまでの流れを10項目にわけて説明します。基本的に、最初の1が成功すれば、あとはスムーズに進んでいくケースが多いため、ペット可物件の経験則が高い不動産管理会社と契約するのは重要なポイントといえます。
- 不動産管理会社に相談する
- 既存入居者にアンケート入居条件を決める
- 飼育条件を決める
- 違反時のペナルティを決める
- 共用部分のルールを決める
- 既存入居者に同意を得る
- 必要なリフォームなどをする
- 募集開始入居後の対応を慎重に行う
3-1.不動産管理会社に相談する
空室対策のためにペット可を検討していることを、不動産管理会社に相談します。ペット可物件は、不動産管理会社の営業方針によって考え方が違うため、反対される可能性もあります。
オーナーとしてはペット可以外の方法でも、空室対策ができて、経営状態が改善されれば良いのですから、反対意見は良く聞いてから、総合的に判断してください。どうしてもペット可で対策をしたい、または、不動産管理会社にペット可物件の経験則がなくて不安な場合は、管理会社を変更することも視野に入れてみてください。
空室対策としてペット可物件にすることを検討中であれば、まずはペット可物件に経験と実績のある不動産管理会社に相談をしてみるのがおすすめです。他の会社に契約中でも、他の会社に相談をすることはまったく問題ありません。
また、管理会社はいつでも自由に変更できますので、まずはたくさんの管理会社のプランと価格を比較してみてください。NTTデータグループが運営する「賃貸経営HOME4U」の賃貸管理一括無料相談サービスならば、今現在の空室の改善からペット可まで、賃貸経営で起きるさまざまなシーンに適切な提案をしてくれる、頼りになる不動産管理会社との出会いがあります。
3-2.既存入居者にアンケート
現在の入居者は、建物内にペットがいないことを前提に賃貸契約をしていますので、ペット可の導入は、先に住んでいる方々の理解と承認が必要です。このような段階をふまずにペット可にしてしまうと、万が一、既存入居者の中にアレルギーの方がいた場合、重篤な健康被害が出る可能性もありますので、かならず既存入居者への確認をしてください。
また、動物への恐怖心が強い方であれば、同じ棟内に動物がいると思っただけで、精神的に大きなストレスになる可能性があります。空室対策のためにペット可にして、既存入居者が退去してしまうと、空室対策にならなくなってしまいます。
このような理由から、先に住んでいる方々には、必ずペット可物件にすることへのアンケートを取り、全員の同意を得てから進めるようにします。具体的には、書面やメールなどでアンケートの回答をもらい、全員の意向やアレルギーの有無などを調べたうえで、慎重に検討していくようにします。
3-3.入居条件を決める
アンケートの結果、大きな反対がなければ、室内で飼育できるペットの種類や数など、オーナーと一緒に入居できるペットの条件を決めます。以下は、ペット可物件で許可されている、一般的なペットの入居条件です。基本的に、どのペットでも繁殖はできません。
| ペット | 飼育めやす |
|---|---|
| 犬 | 小型 チワワ・ミニチュアダックスなど10kg以下 最大2匹中型 ビーグル・スピッツ・柴犬など25kg以下 1匹大型 ゴールデンレトリバーなど 25kg以上 応相談 |
| 猫 | 種類に限らず最大2匹まで・多頭飼い応相談 |
| うさぎ・ハムスター | 種類に限らず1~2匹まで・多頭不可・ハムスターは室内放し飼い不可 |
| 小鳥・オウム類 | 応相談・室内放し飼い不可 |
| 爬虫類 | 小型であればOK・多頭不可・室内放し飼い不可 |
飼育をしてよいペットとその条件は、オーナーと不動産管理会社で決めていきます。ペットを限定したら、入居の際に以下の条件を承諾できる飼い主(入居希望者)のみを、入居可にします。
- 犬は狂犬病予防法における飼い犬登録・狂犬病予防接種を実施する
- 犬猫など感染症予防のためのワクチン接種を実施する
- 個人賠償責任保険に加入する
- 動物飼育細則を遵守する
- 誓約書を提出する
- ペットの逃走などは飼い主が責任をもつ
このような細かなルールつくりが、ペット可物件と賃貸経営を成功させるポイントになるので、経験則のある不動産管理会社の存在は不可欠です。
3-4.飼育条件を決める
ペットの飼育条件と生活ルールを決めていきます。物件の構造や入居者タイプによって飼育ルールが変わりますので、経営中の物件の状態に合わせたものを作成してください。基本的に、以下の項目がしっかり守られていれば、大きなトラブルにはつながりにくいと言えます。
- 飼い主不在時は窓を開けっぱなしにしない
- 飼い主の外出時は戸締りを厳重にする
- 旅行や出張時はペットだけの留守番にしない
- 飛び出し防止策など安全対策をする
- 犬はマテ・オスワリ・ダメなどをしっかりしつける
- ベランダで飼わない
- 浴室でのトイレは禁止
- 糞尿の始末は飼い主が責任をもって行う
- 階下への足音防止にカーペットなどを敷く
- ダニ・ノミが発生しないように定期的なケアをする
- 夏と冬は、特に室内温度に気を付ける
【参考:環境省 住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン】
3-5.違反時のペナルティを決める
すべてのペットオーナーがルールを守ってくれるとは限りません。ルール違反をした場合には、ペナルティが発生するようにするなど、ペット可物件にしたことにより、建物全体の秩序が乱れないようにする必要があります。
ペナルティには罰金以外にも、建物の共用部分の清掃奉仕・ペット飼育セミナーへの参加など、違反をした入居者の理解を促すようにするなども効果的です。再三の注意や指導にも従わない場合も想定し、強制退去を命じられるような契約書作成も検討しておく必要があります。これは、ペット可用の契約書を作成する前の段階で、不動産管理会社と相談し、準備しておいてください。
3-6.共用部分のルールを決める
入居者全員が利用する場所(共用部分)でのルールを決めておきます。たとえば、以下のような共用部分のルールを設けておくと、トラブル発生の可能性を低くするのに役立ちます。
- 共用部ではキャリーケースに入れるか抱きかかえて移動
- 散歩後はペットの足洗い場・ウエットティッシュなどできれいにする
- ペットの被毛処理は室内で行う 集合住宅では、ベランダやバルコニーも共用部分です。被毛のケアなどは室内で行い、共用部分でのケアは不可とします。
- 敷地内での散歩は原則NGとしておく
共用部ではほかの入居者に迷惑をかけたり、共用部を汚したりといったことが無いように、小型犬であれば抱きかかえる、それ以外はキャリーケース・ペットカートなどに入れて移動させるようにします。
散歩ではどうしても外部の土や汚れが付着しますので、建物内に持ち込まないようにエントランスに入る前に手足を拭いてあげます。
アパートやマンションの敷地内は入居者の共用部分です。広い庭や駐車場があるような場合でも、そこでの散歩はしないようにしておきます。
3-7.既存入居者に同意を得る
ここまでの項目がすべて出来上がったら、一度、既存入居者に内容をお知らせします。個別に郵送・メール添付で内容に同意してもらい、署名をしてもらいます。内容に加筆修正をする必要があれば、そのたびに既存入居者に確認を取ります。
この段階で、既存入居者全員の同意が得られない場合は、反対を表明する既存入居者が退去をしてからペット可にするようにしてください。この方法が、最もクレームとトラブルを回避できる確率が高くなります。それまでの間は、他の空室対策で対応しながら、タイミングを待ちます。
3-8.必要なリフォームなどをする
準備が整ったら、空室となっている部屋に、ペット可に対応するリフォームなどをします。基本的に、キズの付きにくい床材、ニオイの付きにくい壁紙などを予算の範囲内で行い、後は入居者責任で防汚・防音対策をしてもらうので問題ありません。
1つのペット可による空室対策が功を奏せば、そのほかに退去が起きたときには、もう少し積極的なペット可用の内装にするなど、ペット可の空室対策用リフォームは、様子を見ながらすすめてください。
原状回復工事をしていない状態であれば、必要なキッチン・バス・トイレの点検・修理・交換などもしておきます。
3-9.募集開始
ペット可物件としての入居者募集を開始します。不動産ポータルサイトで、ご自分の物件がペット可で検索して出てくるのか、かならず確認してください。同エリアのペット可物件をチェックし、画像や動画など、どのようなアピールをしているかを見て、真似をしてみてください。
はじめは空室対策として始めたことでも、もしかしたら、物件にとっての強みになり、経営状態改善に大きな効果が出る可能性があります。現在、入居者がいるお部屋も含め、将来的に全室をペット可にする可能性も含めて、ライバル物件はしっかり観察しておいてください。
3-10.入居後の対応を慎重に行う
ペット可物件に入居者が決まり、1~2カ月ほど経過したら、既存入居者とペット可入居者の両方にアンケートを取り、トラブルの前兆がないかを確認してください。自由に書ける欄を大きくしておくことで、たくさんの書き込みが増える傾向があります。
たとえば、犬の吠える声が気になる、早朝や夜の散歩のときの足音や声が大きいなど、ペットに対してだけではなく、今まではなかった物音・ニオイ・光・話し声などに反応することがあります。ペット可で入居した方にも、周りに厳しい態度を取られなかったかなど、入居者全体の関係性にも注意をしてください。
あまりうまくいかないようであれば、現在のペット可物件だけで募集はいったん終了し、空室がある場合は、他の空室対策で対応するようにしてください。
4.ペット可での空室対策5つの原状回復費カバー法
ペット可で入居した方が退去するお部屋には、今までとは違ったことが起きている可能性が高くなります。室内だけではなく、共用部分のダメージも増えている可能性があり、予想外の費用が発生する可能性もあります。
本章では、将来的な原状回復費用を十分にカバーできる状態にしておくために、ペット可をスタートする前に準備しておく5つの対策方法をまとめています。どの方法が適切なのかは、エリアの慣習と、物件状況によっても違いがあります。不動産管理会社と相談しながらすすめてください。
- 敷金・礼金を上乗せする
- 原状回復費用を賃料に上乗せしておく
- 退去時の状態にかかわらず必ず支払う退去費用を設定する
- 契約書に「敷金償却・敷引き」の特約をつけておく
- 入居者の故意過失による原状回復費用は全額入居者負担
4-1.敷金・礼金を上乗せする
ペット可物件の敷金・礼金は、エリアによって違いはありますが、敷金1か月上乗せが一般的です。たとえば、敷金・礼金で2カ月ずつ合計4カ月の物件であれば、ペット可は敷金3カ月分を原状回復費として使えることになります。
飼い主は、ペット可物件に敷金の上乗せがあることは承知していますので、このことで問題が発生する可能性は、ほぼないと言えます。敷金礼金は、システム自体がない地域もあり、保証金のような形で賃料2~3カ月分を入居時に徴収し、退去時には返金しないという方法をとっているところもあります。
ペット可物件の原状回復費にいくらかかるのかは、建物の構造や間取りによっても変わってきます。不動産管理会社にエリア相場を確認してもらい、経費オーバーにならないようにシミュレーションしてください。敷金礼金は地域性がありますので、物件のあるエリアの慣習に従うようにしてください。
4-2.原状回復費用を賃料に上乗せしておく
敷金礼金システムがない、敷金ゼロにしている、フリーレント方式を採用しているなどの場合は、原状回復費を確保する方法として、あらかじめ賃料に上乗せしておく方法があります。一般的な契約更新は2年なので、2年後に退去が起きた場合に、必要な金額が用意できているように賃料設定をしておきます。
たとえば、原状回復費に30万円が必要であれば、30万円÷24ヶ月=12,500円/月 が上乗せ金額です。賃料が10万円設定のところを、12.5~13万円に変更して募集をします。
賃料は高めになりますが、敷金礼金などの大きな初期費用が必要ないぶん、ペット可物件を探している入居者にとっては、負担にはならない傾向があります。
4-3.退去時の状態にかかわらず必ず支払う退去費用を設定する
敷金がなく、さらに前項のように原状回復費を賃料に上乗せしたくない場合は、ペット可物件用の原状回復費として「退去費用」を決めておき、退去時に部屋が汚れていようがキレイであろうが、決めていた金額を支払ってもらう契約をします。 たとえば、退去費用を賃料3カ月分と決めておき、退去時にその金額で原状回復費を清算する方法です。退去費用でカバーするのは、ペット可物件によくある以下のような部分です。
- 壁紙の汚れ・キズ・破れ
- フローリング・畳のキズ
- 柱や角のキズ
- ふすま・障子の汚れや破れ
- ペットのにおい
契約書には、上記の原状回復費用をすべて含んだ金額として退去費用の支払いをする旨を記載し、それに承諾できる方のみを入居審査に通すようにします。契約前にこのような取り決めがされていなかった場合、原状回復費の負担をどちらがするのかで、トラブルになる可能性があります。
退去費用は賃料の〇ヶ月分でも、原状回復費の工事代金でも構いませんが、エリア相場から大きく外れないようにしてください。不動産管理会社にも相談をし、ペット可を運営している他の物件を参考にしながら、適切だと思われる価格を決めていってください。
4-4.契約書に「敷金償却・敷引き」の特約をつけておく
敷金・礼金のシステムは、エリアによって少しずつルールが違うため、自分の思っている敷金礼金のルールが、お部屋探しをしている方と同じ理解だとは限りません。入居者にはさまざまなエリアからの出身者がいますので、契約書には「敷金償却・敷引き」の特約を明記しておく必要があります。
敷金とは、契約期間中に起きる家賃滞納・物件損傷時の修理費として、先に預かっておくお金のことです。退去時には、預かった敷金から原状回復費用を差し引いて(敷金償却・敷引き)、お金が余ったら、借主に返却するのが一般的です。
しかし、ペット可物件は部屋が汚れることが大前提であるため、預かった敷金をほぼ満額使って原状回復をします。そのため、契約書にあらかじめ、敷金償却・敷引きの文言を入れておくことにより、「預かった敷金は、ペットが汚した部屋の原状回復に使うので返しませんよ」と言っているのと同じことになります。
契約書にはこの文言を入れておき、さらに契約時には口頭で内容を説明しておかないと、退去時に「うちの実家のほうでは、敷金は返って来るものだった」「敷金のためにキレイに使っていたのに!」などの退去トラブルを引き起こす原因となります。
4-5.入居者の故意過失による原状回復費用は全額入居者負担
契約書にある「してはいけない」行為をした結果、部屋の汚れ・破損が起きた場合は、それが入居者の故意・過失に関わらず、原状回復費は入居者負担となります。たとえば、壁やドアにリードフックを打って穴があくのは故意、ペットがドアや壁を噛んでボロボロになるのは過失です。
何をもって故意・過失とするのかは、現状の物件の状態や構造にもよりますので、国土交通省のガイドラインを参考に、不動産管理会社と一緒に契約書つくりをしていきます。
【参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」】
5.ペット可で空室対策を行うときの4つの注意点
ペット可を採用するかどうかの検討段階で、オーナーが以下の4点を理解しておくと、空室対策がスムーズになります。
- 他の空室対策で対応できないか検討する
- 敷金と原状回復費の違いを理解しておく
- 音とニオイの問題はオーナー側でも適切な対処をする
- ペット可に実績のある不動産管理会社をパートナーにする
5-1.他の空室対策で対応できないか検討する
空室対策には、ペット可にする以外にもさまざまな選択肢があります。ペット可にするためには、既存の住人も巻き込んでいく必要があるため、はじめるとなると、かなりの時間と労力が必要です。また、一度ペット可にしてしまうと、ペット可物件として借りた方は長期更新になる可能性が高いため、ペット不可に戻しにくくなります。
運よくペット可→ペット不可に戻せても、ペットを飼わない方にとって、一度でもペット可になった物件は、一般の賃貸とは違うものとして認識されます。そのため、以前の状態とまったく同じに戻すことはむつかしいと思っておいた方が良いと言えます。
空室にお悩みで、空室対策としてペット可をお考えの場合は、他の空室対策を検討したうえで、ペット可が最適だと判断できた場合にのみ、先にすすめるようにしてください。その他の空室対策に関しては、以下の関連記事を参考にしながら、管理会社にも相談をしてください。
5-2.敷金と原状回復費の違いを理解しておく
ペット可にすると、原状回復の内容が、今までと変わることを理解しておく必要があります。原状回復とは、お部屋を入居時の状態に戻すことです。たとえば、生活ヨゴレのついた壁紙の張り替えや、日常生活による細かなキズがついたフローリングの補修、室内設備の修繕などが含まれます。
国土交通省が示している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、ペットを飼育したことによって起きた、室内のキズや汚れは、通常の使用によるものとはみなされないため、お部屋を借りた方が費用負担するのが妥当であるという文言があります。
一般的な賃貸で敷金を預かっている場合、入居者が支払うべきキズや汚れがあれば、その分の原状回復費が敷金から差し引かれ、残金が返金されます。しかしペット可の場合は、預かっていた敷金だけでは、原状回復費をカバーできないことがあり、足りない金額は追加で請求しないと、オーナーが自分で負担することになります。
今までの一般賃貸と同じように「敷金でカバーすればよいか」と軽く考えていると、思わぬ損失が発生する可能性があります。ペット可物件の原状回復費が実際にいくら発生するのかは、物件の構造や築年、間取りなどによっても変わります。ガイドラインを参考に、不動産管理会社と相談をしたうえで、適切だと思われる金額を算定しておき、確実にカバーできるような、家賃設定を考える必要があります。
5-3.音とニオイの問題はオーナー側でも適切な対処をする
既存入居者からペット可への承諾をもらっているとしても、ペットを飼っていない方への音やニオイへのケアは、オーナー側でも十分に配慮しておくべきといえます。
ペットも生き物ですから、ペットの生活音があります。たとえば、犬や猫の床を歩く・走る音、ウサギがケージの床を掘る・蹴る・掻く音、夜中にハムスターが動く音など、さまざまな音があります。音の感じ方は人によって違いますので、気にならない方もいれば、騒音のように感じる方もいます。
5-4.ペット可に実績のある不動産管理会社をパートナーにする
空室対策としてペット可物件を検討している方は、まずは、経営中の物件の状態を理解し、ペット可を含めて空室対策を提案してくれる、賃貸経営と賃貸管理のプロフェッショナルの存在が必要です。
そのためには、現在契約中の不動産管理会社も含めて、たくさんの会社を比較しながら、適切な空室対策のアイデアを提案できるパートナー探しをしてください。
NTTデータグループが運営する「HOME4U賃貸管理」の賃貸管理一括無料相談サービスでは、一回の入力で、現在経営中の物件と相性の良い不動産管理会社を、数多く見つけることができます。ご所有の物件のエリアと物件種別を選んだら、賃貸管理・仲介・サブリース・いろいろなプランの提案が欲しい、という項目がありますので、希望するサービスにチェックを入れます。
送信ボタンの最後には「ご要望」という欄があるので、そこにペット可を検討中と記載しておけば、ペット可が得意な不動産会社が見つかりやすくなります。希望した連絡方法で不動産管理会社から連絡が入りますので、感触の良さそうな会社があれば、面談もかねて、会って話を聞いてみてください。空室対策としてのペット可物件化も含め、今の経営状態を判断したうえで、経営プラン・管理プランを提案してくれますので、納得のいくまで絞り込んでください。
まとめ
空室対策としてペット可物件を導入しようとご検討中のオーナー向けに、知っておくべき内容をやさしくまとめました。
ペット可にすると、既存入居者とペット可入居者が混ざって住むことになりますので、オーナーとしては事前対策をしっかりしておくべきといえます。
ペット可物件は、空室対策としての選択肢のひとつですが、不動産経営と不動産管理のプロフェッショナルに相談することで、より良い空室の解決方法が見つかる可能性があります。
まずは、たくさんの管理プランを請求し、なるべく多くの管理会社に相談をするところからスタートしてください。