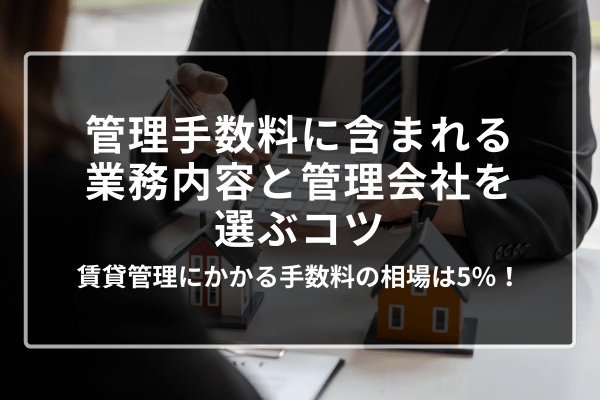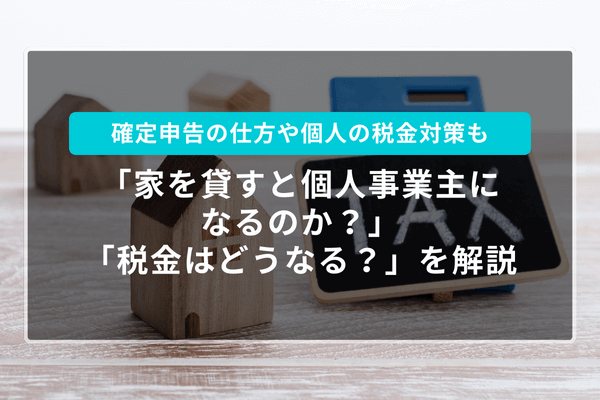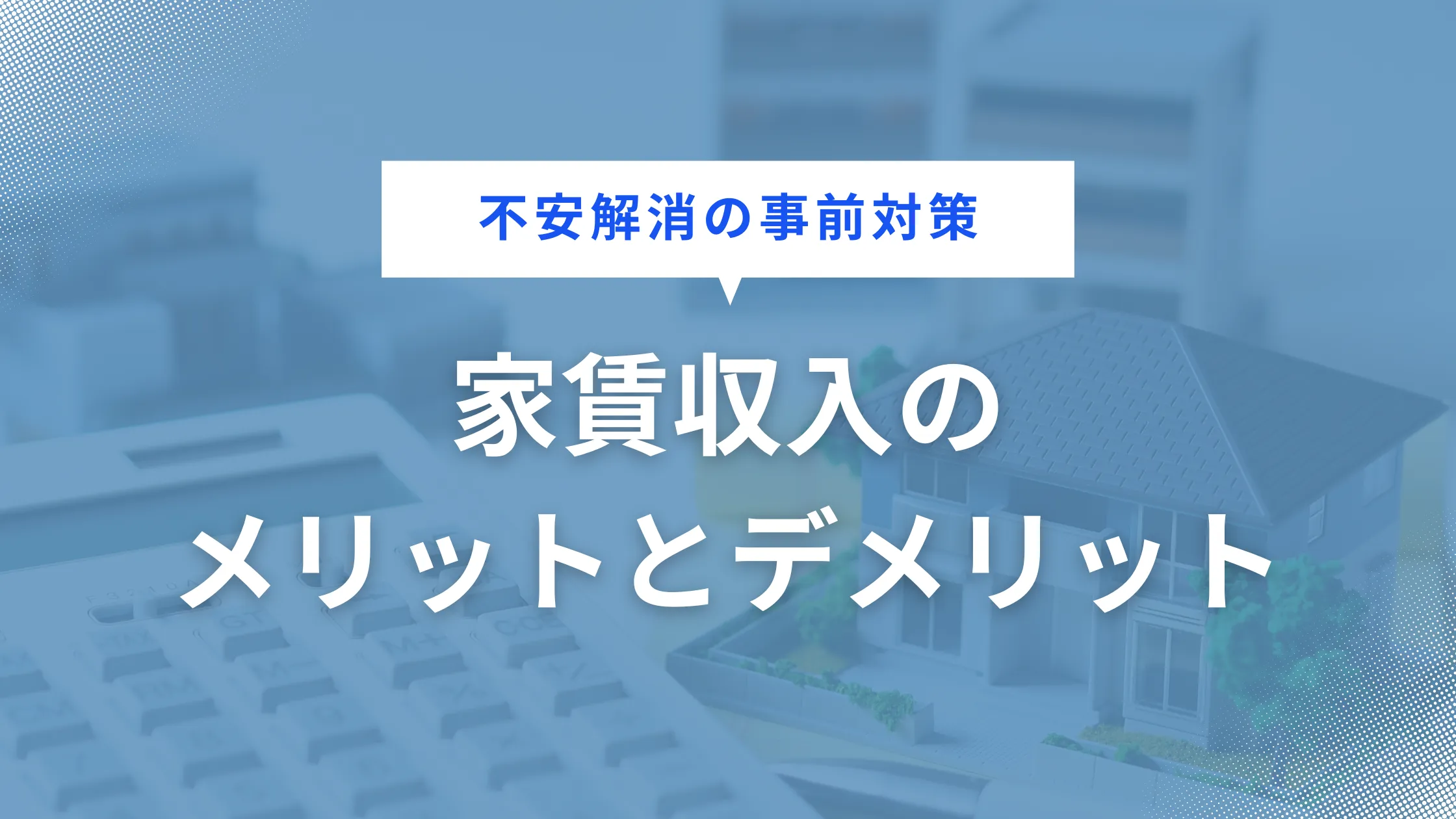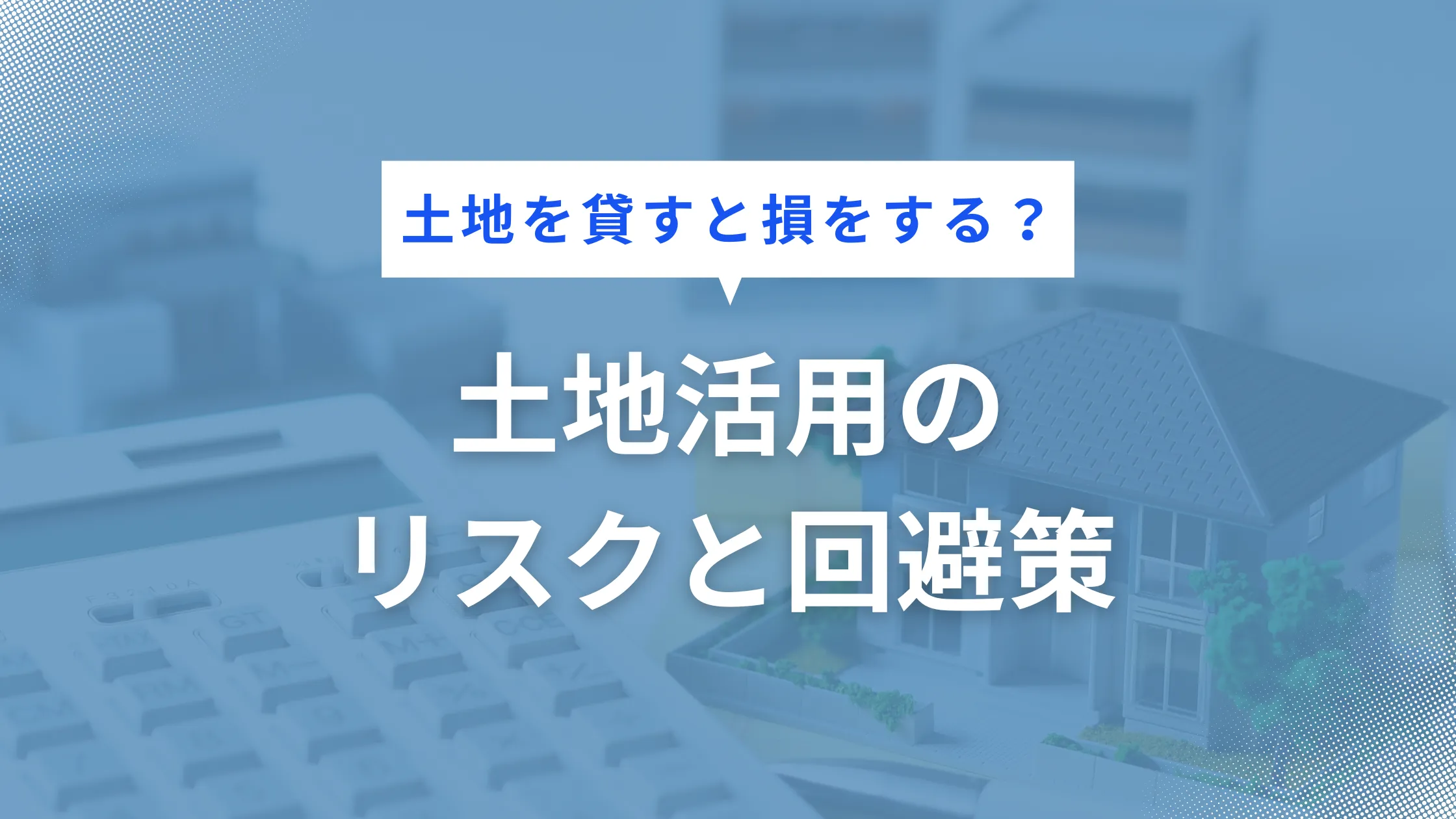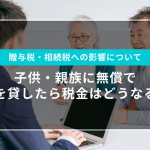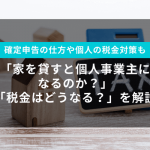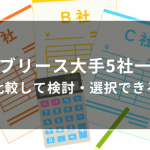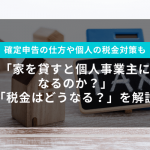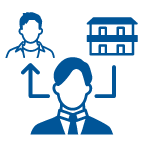不動産投資・土地活用でできる節税対策と節税効果の高い4つの不動産投資先

不動産投資に関して調べていると「節税ができる」という内容の記事がたくさん見つかります。節税は気になるけれども、専門的な記事が多いため、読んでみてもあまり良く理解できないことも多いかと思います。今回は、はじめての不動産投資・土地活用のどちらでもわかる、不動産への投資と節税に関したことを、やさしくまとめています。
1.不動産投資で節税が期待できる主な税金4種
土地活用を含めた不動産投資で、節税が期待できるのは次の4種の税金です。それぞれ、どのような税金なのかを、かんたんに説明します。
- 固定資産税・都市計画税
- 所得税・住民税
- 相続税
- 贈与税
1-1.固定資産税・都市計画
固定資産税は、毎年1月1日現在で不動産を所有している方に、毎年かかる地方税です。都市計画税は、ご所有の土地が市街化調整区域にある場合のみ追加で課税されます。
土地を住居のために使うと、固定資産税に「住宅用地の特例」が適用され、税率が軽減されます。固定資産税は、更地の状態が最も税額が高く設定されていますが、軽減措置が適用されると以下のように税率が下がります。
- 小規模住宅用地(200平米以下):課税標準額が1/6に軽減
- 一般住宅用地(200平米超):課税標準額が1/3に軽減
たとえば、400平米の更地にアパートやマンションなどの住居を建てれば、土地の半分が1/6、残り半分が1/3まで、固定資産税が軽減されます。更地で土地をご所有の場合は、アパートやマンション経営などの不動産投資をすることにより、毎年の固定資産税負担を大きく減らすことができます。
現在、ご所有の土地に、毎年いくらの固定資産税を支払っているのかは、6月頃に郵送されてくる固定資産税納付通知に同封された課税明細書で確認できます。
【参照:東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)】
1-2.所得税・住民税
所得税は、1年間の収入から経費を差し引いた「所得」に対しての課税です。賃貸経営では、ローンのための費用、経営のための費用、建物の減価償却費など、必要経費を多く計上することにより、所得税と住民税をおさえることができます。
減価償却費とは、その物件の取得価格(購入価格・建築費)を一度にぜんぶ経費計上せず、法定耐用年数という基準に沿って、毎年費用として計上していくという、会計上の考え方です。「お金の支出がない帳簿上の費用」という特徴があるため、減価償却費分だけ所得を大きく圧縮できます。
さらに、不動産投資が副業である場合は、本業の収入から副業の赤字分を相殺する「損益通算」ができますので、さらに所得税課税額が減り、ケースによっては払い過ぎた税金が還付されることもあります。住民税は所得税に連動していますので、所得税が減ると、自動的に住民税も軽減します。
【参照:国税庁 減価償却費のあらまし】
1-3.相続税
不動産投資・土地活用とも、相続税対策として大きな節税効果が見込めます。相続開始時点で、故人のすべての財産は相続税の対象になります。このとき、現金はそのままの評価額になりますが、生前に現金を不動産にかえて持っていると、相続税評価額を下げることができます。
さらに、人に貸すための不動産として、借金をしてアパートやマンションを所有することにより、ローン残債が相続税課税額から差し引かれ、貸家建付地の特例や小規模宅地の特例などが適用され、大きく課税額を下げることができます。
不動産投資・土地活用による相続税対策をご検討の方は、かならず、税の専門家と法律の専門家にも相談をしてうえで判断するようにしてください。
【参照:土地家屋の評価】
【参照:貸家建付地の評価】
【参照:小規模宅地等の特例】
1-4.贈与税
贈与とは、個人が自分の財産を、指定した人物へ無償で与える契約のことをいいます。贈与には、生前贈与と死因贈与があり、後者の死因贈与は亡くなったことによって契約の効力が生じるタイプの贈与であるため、一般的に節税対策における「贈与」とは、生前贈与のことを指します。
生前贈与をすると贈与税がかかりますが、あらかじめ、贈与対象を現金から不動産にかえておくだけで、贈与税の課税評価額を下げることができます。たとえば、現金1,000万円をそのまま贈与するよりも、1,000万円のマンションを購入してから贈与をすれば、贈与対象の固定資産評価額で課税額が決まります。多くのケースで固定資産評価額は市場価格の60%程度ですので、大きな節税につながります。
生前贈与にかかる贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、暦年課税では年間110万円の控除額までは無税、100万円を超えた部分に課税されます。相続時精算課税は、贈与を受けたときには控除額2,500万円までは贈与税が発生せず、2,500万円以上の部分にだけ贈与税がかかります。
贈与者(あげた人)が亡くなって相続が開始すると、贈与を受けた財産額を、その他の相続財産と一緒にして相続税を計算し、すでに納税してある贈与税額を相続税額から差し引きます。贈与を行う前には、事前に税務相談と法律相談の両方をしておき、相続税のことも含めて慎重に判断する必要があります。
【参照:国税庁 贈与税がかかる場合】
2.節税効果が期待できる4大不動産投資方法
不動産投資の中で、節税効果が期待できる方法を4つにまとめて説明します。不動産投資や土地活用の目的は、あくまで「長期的に安定した賃料収入」であり、節税効果は副次的なものであることを前提に、投資先を考えるようにしてください。
|
アパート経営 |
戸建て賃貸 |
事業用定借 |
福祉施設賃貸 |
|
|---|---|---|---|---|
|
固定資産税・都市計画税 |
◎ |
◎ |
△ |
〇 |
|
所得税・住民税 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
相続税 |
◎ |
◎ |
〇 |
〇 |
|
贈与税 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
2-1.アパート経営
アパート経営はアパマン経営とも呼ばれ、入居者から賃料を得る目的で、集合住宅を経営することです。アパート経営の「アパート」は、アパート・マンションなどを含めた集合住宅の総称です。経営する集合住宅には、木造・鉄骨・鉄筋コンクリート造など複数の選択肢があります。
土地を持っている方は、ご所有の土地にアパートやマンションを建てて、遊休地の活用をするのが一般的です。土地をお持ちでない方は、マンションの区分1室からスタートする、経営中のマンションを一棟丸ごと購入する、土地建物を購入してアパート経営するなどの投資方法があります。どの方法であっても、アパートローンを使って物件購入(建築)をし、入居者家賃でローンを支払っていきます。
不動産投資による節税効果
どの方法であっても、貸し出すのは住居であるため、住宅用地の特例によって固定資産税は更地の1/6まで下がります。所得税・住民税は賃料収入から戸数分の経費と減価償却費が差し引かれます。
相続では、手持ちの現金をアパートなどにかえておくことで、相続税評価額を下げることができます。アパートローンはマイナスの財産として相続税の課税対象になりますので、税額を大きく下げることができます。人に貸している土地建物であるため、貸家建付地と小規模宅地の特例の両方が適用されます。
経営中の賃貸住宅を贈与すると、贈与された方(受贈者)に贈与税と賃料収入が発生します。親から子へ贈与した場合、子に贈与税と賃料収入分の所得税・住民税が発生しますが、親は贈与した分だけ節税できます。
2-2.戸建て賃貸
人に貸すことを前提として一軒家を建てる、または中古住宅を貸し出すなどで、賃料収入を得る方法で「貸家」とも言います。最近では、古くなった実家を壊したり売ったりせず、リフォームして貸し出すことも、不動産投資方法として注目されてきています。
2-3.不動産投資による節税効果
アパート経営と同様に、住居として貸し出すため、住宅用地の特例が適用され、更地と比べて固定資産税は1/6まで下がります。しかし、もともと土地に建っていた家屋を貸し出す場合は、固定資産税に変化はありません。
戸建賃貸は1戸に1入居者(家族)が前提であるため、戸数のあるアパート経営と比較すると、運営経費は少な目です。相続税では貸家建付地と小規模宅地の特例の両方が適用できます。アパートローンはマイナスの財産として、相続税課税対象額から差し引かれますので、大きな節税効果が期待できます。
贈与税は、贈与された方(受贈者)に贈与税と賃料収入が発生します。親から子へ贈与した場合は、子に贈与税と、贈与分の所得税・住民税が発生しますが、親は贈与した分だけ節税できます。
2-4.事業用定期借地
固定資産税の負担が重いが土地を手放したくない、
アパートやマンション経営をすることに抵抗がある場合は、企業に土地を貸し出し、事業以外の目的に土地を使わない契約にする、事業用定期借地という不動産投資方法があります。
事業用定期借地権には、契約期間が10年以上50年未満というしばりがあり、退去する時の条件も話し合いで決めることができます。たとえば、契約期間10年で借地期間を満了させ、相続対策をするタイミングで、更地にして戻して返してもらうなど、フレキシブルな条件での貸し出が可能です。
この方法であれば、持っているだけで毎年発生する固定資産税の支払い負担と、賃貸経営をする心理的な負担からも解放されます。
2-5.不動産投資による節税効果
事業用の土地として貸し出すため、ほとんどの特例は適用外になりますが、貸出先が企業であるため、賃料は高額になることが多く、税金支払いには困らなくなる傾向にあります。貸与した土地での事業は企業が経営しているため、経営リスクも低く、最低10年からの長期安定収入を確保できます。
この不動産投資でオーナーが負担する税金は、固定資産税と所得税です。固定資産税は、土地の上に何が建っていても、更地と同じ扱いになります。所得税・住民税は、年間の賃料収入から固定資産税などの必要経費を差し引いた分に課税されます。
相続税・贈与税ともに、借地権の残存期間に応じて15年以上20%、10~15年で15%、5~10年で10%、5年以下で5%という評価減割合がありますので、定期借地中に相続が起きても節税はできます。契約中に相続・贈与が起きても、土地の貸与契約は期間満了まで継続しますので、所有者が変わるだけで、賃料収入もそのまま継続します。
このように、活用しにくい土地は企業に貸し出して税金を支払い、さらに、定期借地からの利益と手持ちの現金を使って、より節税のしやすい不動産投資に投下することもできます。
【参照:国土交通省 定期借地権の解説】
2-6.福祉施設賃貸
福祉施設運営は、介護サービスの有無による経営内容の違いはありますが、節税効果の大きい投資方法と言えます。福祉事業がはじめての方でも参入しやすいものには、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)やグループホームなどがあります。
特定のサービスがついているアパート経営という立ち位置であるため、入居者とテナントからの家賃が主な収入になります。施設に必要なサービスは専門会社が行い、オーナーは施設を提供するという経営スタイルが一般的です。
福祉施設であるため、マンションやアパート経営には適していない土地条件であっても、入居者やテナントには困らない傾向があり、賃貸住宅経営としても、節税対策としても注目されています。
2-6.不動産投資による節税効果
サービス付き高齢者向け住宅を例に解説をします。サ高住は「住居」であるため、はじめから固定資産税の住宅用地の特例が適用されており、固定資産税は更地の1/6です。そこからさらにサ高住の特例適用により、経営開始から最初の5年間は、1戸当たり120平米まで、1/2~5/6までの範囲で固定資産税を減額できます。
所得税は、新築から5年間にわたり、40%の割増償却ができるようになります。相続税に関しては、一般のアパート経営をするときと同じく、小規模宅地・貸家建付地の特例などが適用できます。
新規に不動産を取得した時に発生する不動産取得税は、1戸当たり1,200万円まで控除されますので、実質、不動産取得税の支払いはありません。また、サ高住を建築の融資制度と、建築費とサ高住に必要な設備などに関して補助金が複数用意されています。
【参照:国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅】
不動産投資には、土地条件や資金条件によって投資・節税ともにたくさんの選択肢があります。ご自分の場合は、どのような方法で不動産投資・土地活用にとりくめば、効果的な節税になるのかは、プロフェッショナルに相談しながら決めていく方が良いと言えます。
NTTデータグループの運営する「賃貸経営HOME4U」の一括プラン請求であれば、土地活用・不動産活用のスタート時点から、経営開始後までをトータルにプロデュースし、的確なアドバイスができる不動産会社を探し出すことができます。
3.不動産投資と節税に関した素朴な10のギモンQ&A
不動産投資に興味があり、節税のことも頭にあるオーナーに向けて、不動産投資と節税との関係性に関した素朴な疑問をあつめてみました。
- 不動産投資と土地活用にはどういう違いがあるの?
- 空き地の固定資産税額がすごいので、何か対策をしたい。
- 節税の話に出てくる減価償却ってなに?
- どうして節税になるの?
- アパートやマンション経営が節税に有利って本当?
- 投資用不動産を取得したときに払う不動産取得税も節税したい。
- サラリーマンが不動産投資をしても節税ができるのですか?
- 節税目的で不動産投資をしても大丈夫でしょうか?
- 不動産投資の収入には消費税がかかりますか?
- 経営中のアパートが黒字で税金がすごい。
- 節税対策したい。
- 不動産投資・土地活用の相談ができる不動産会社を探したい
Q1:不動産投資と土地活用にはどういう違いがあるの?
A:不動産を使って賃料収入を得るのも、使える制度も、ほぼ同じです。
不動産に投資をして賃料収入を得るという意味においては、土地活用も不動産投資も同じですが、スタート地点が違います。
使っていない土地を有効活用するのが土地活用ですので、土地活用をするためには、遊休地を持っている必要があります。土地は持っているだけでは固定資産税などの負担があるため、管理負担を軽くし、さらに利益が出ることが、投資をする主な目的になります。
不動産投資は、収益不動産を買って運用することです。目的が不動産を通じて利益を得ることに特化していますので、将来的には売却してトータルでプラスにするのが一般的です。売却のためには流動性の高さも必要であるため、区分ワンルームマンションなどの、買いやすく売りやすい物件が、主な投資先になる傾向にあります。
このようにスタート地点による差はありますが、物件に適用できる特例・制度などはほぼ同じであるため、得られる節税効果という意味でも同じと言えます。
Q2:空き地の固定資産税額がすごいので、何か対策をしたい。
A:空き地・更地は、最も税額が高い状態です。土地活用で解消します。
土地には「住宅用地の特例」という減税制度があり、土地に住居が建っていると、それだけで固定資産税が1/6にまで、都市計画税は1/3まで減額される制度が適用されます。
住宅用地の特例には、人が住んで生活をするための場所には、税負担を軽くするという目的があります。つまり、人が住んでいない=住居がない土地に対しては、減額しませんよというものです。
ご所有の土地が更地の場合は、土地活用として住宅を建築すれば、すぐに特例が適用されます。人に貸すための賃貸住宅でも「住宅」として適用されますので、同じ建てるのであれば、アパート経営などの賃貸経営をするほうが、賃料収入によって固定資産税の支払いもでき、さらに収入を得ることもできます。
Q3:節税の話に出てくる減価償却ってなに?どうして節税になるの?
A:減価償却とは会計上の価値のめやすです。支出がないのに経費計上できます。
減価償却とは、不動産を買った時の金額を、法定耐用年数で分配するという会計上の考え方です。法定耐用年数とは「この資産はだいたいこのくらいの期間は使えるよね」という考え方のもとに、価値の残存期間めやすとして設定したものです。
不動産の法定耐用年数は、木造で22年、鉄筋コンクリート造で47年です。木造アパートの土地活用であれば、アパートを建てた時の建築費を22年で割ったものが、毎年の減価償却費相当※1になります。土地は減価償却をしないため、土地建物の両方を購入して不動産投資をした場合は、建物にしか減価償却費は発生しません。
減価償却によって節税できるのは、所得税と住民税です。以下は、減価償却費と節税に関したシンプルな計算例です。
計算例)新築木造アパートの建築費が4,400万円だった場合
- 法定耐用年数 木造 22年
- 毎年の減価償却費 4,400万円÷22年=200万円(※2)
- 毎年の賃料収入合計 500万円
- 諸経費 50万円
- 所得税課税額 500万円-(諸経費50+減価償却200)=250万円
※1例としてわかりやすくするために均等に割っていますが、実際には毎年の償却費を差し引いたものから再計算されますので、減価償却費は初年度が最大となり、年々小さくなります。※2初年度の値段です。
上記例のように、アパートを建築すると、初年度には多額の建築費がかかりますが、完成後に建築費は発生しません。支出が発生しないのにもかかわらず、建築にかかった費用は、減価償却費として毎年計上できます。つまり、減価償却費は現金支出を伴わない費用として、会計上の利益を減らすことになるため、所得税や住民税を軽減する効果があります。
Q4:アパートやマンション経営は節税に有利って本当?
A:住宅用ほど税制面の優遇があるのは本当です。
同じ不動産投資でも、住宅用・店舗用・工場や倉庫などと比較すると、住宅用が最も税制面で有利なのは本当です。たとえば、固定資産税には住宅用地の特例が適用され、税額は更地の1/6になります。これに加えて、令和8年3月31日までに賃貸住宅を新築した場合は、固定資産税が初年度から5年間、1/2に減額される「新築住宅に係る税額の減額措置」も適用されます。
所得税と住民税は、前項でも解説したとおり、減価償却によって、アパート経営初年度から数年間は、大きく税負担を減らすことができます。相続税においては、人に貸している住宅として貸家建付地による評価減、さらには小規模宅地等の評価も適用されます。アパート建築に要したローン残債は、マイナスの資産として評価されるため、相続税課税額を大きく減らすことができます。
住宅以外でも適用される特例もありますが、住宅用の不動産投資ほどではないため、節税効果の大きさで投資先を選ぶのであれば、アパートやマンションの経営をおすすめします。
【参照:新築住宅に係る税額の減額措置】
【参照:不動産取得税の軽減制度】
Q5:投資用不動産を取得したときに払う不動産取得税も節税したい。
A:アパート・マンション経営なら不動産取得税をゼロにすることも可能です。
不動産取得税とは、新しく不動産を所有した時に、自治体から1度だけ課税される税金です。本来であれば、建物評価額の3%分の税額が発生します。(住宅以外は4%)
しかし、マンションやアパートの1室の広さが40~240平米以内/戸という要件をクリアしていれば、不動産取得税の軽減制度が適用され、1戸当たり1,200万円が評価額から控除されますので、ほとんどのケースで課税されることがありません。
以下に、かんたんな計算をしてみます。
- 建物評価額1億円×60%=6,000万円
- 控除額 1200万/戸 ×10室=1億2,000万円
- 不動産取得税 6,000万円-1億2,000万円×3%=0円
不動産取得税の軽減制度を適用する場合は、不動産を取得した日から60日以内に申請する必要があります。この制度は、賃貸住宅は新築のみが対象であるため、中古のマンションやアパートの購入には適用されません。
【参照:東京都主税局 Q12 新築住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか】
Q6:サラリーマンが不動産投資をしても節税できますか?
A:損益通算によって節税も税金還付も期待できます。
サラリーマンのように給与所得がある方は、税金もすべて会社が管理していますので、節税と聞いてもピンとこない傾向があります。しかし、サラリーマンが副業として不動産投資や土地活用をすると、所得税を大きく節税できることがあります。
所得税は総合課税制度であるため、不動産で出た赤字は会社の給与の黒字にぶつけて、通算して課税額を出す「損益通算」が認められています。たとえば、アパート経営が赤字となった年は、会社の1年間の給与所得と合算して所得税を計算します。会社では源泉徴収によって所得税が差し引かれていますので、赤字によって年収が減っていれば、税金の還付が受けられます。
ただし、アパート経営が黒字になった年は、給与収入と不動産収入を合わせた年収はアップしますので、所得税額は増えてしまいます。この場合は、不動産経営による経費を積み上げて節税対策をします。
【参照:国税庁 通算損益】
Q7:節税目的で不動産投資をしても大丈夫でしょうか?
A:節税効果が高いのは、高年収または土地活用のケースのみです。
「節税のための不動産投資」に適しているのは、遊休地を所有していて、固定資産税などの管理費をカバーするための土地活用をする方か、年収が高くて税負担が重いため、不動産を増やしながら損益通算によって所得税を大きく減らしたい方です。
不動産投資に関したネット情報を調べていると、必ず目にするのが「不動産投資で節税ができる」という言葉です。この場合の節税とは、不動産経営が赤字になった時に損益通算によって所得税を節税することと、減価償却費によって所得税を圧縮することの2つになります。
しかし、損益通算は不動産経営が赤字になっていることが前提であり、減価償却は土地には適用できないため、投資に投じた全額が節税対象にはなるわけではありません。特に、土地建物の両方を購入して始める不動投資の場合は、帳簿上も現実にも赤字状態のまま、収益性の低い投資になりやすいと言えます。
不動産投資の本来の目的は、長期安定収入と資産拡大のために資金を投入することにあります。長期的な視点で投資に正面から取り組むことにより、所得税の節税という短期的な利益を追わなくても、税金が楽に払えるだけの経営状態を獲得することは十分に可能です。
ただし、相続税に関しては、手持ちの現金を収益性の高い不動産にかえておくことによって、資産価値そのものが高い状態で、相続税評価額を大きく圧縮できます。そのため、節税目的で不動産投資に取り組む場合は、相続税対策であれば有効な選択肢だと言えます。
Q8:不動産投資の収入には消費税がかかるのですか?
A:住居用の賃貸経営であれば消費税は発生しません。
アパートやマンションなどの住宅用物件の家賃収入は、消費税は非課税です。しかし、住宅用と事業用(テナント・店舗・事務所など)の両方から家賃収入がある場合、事業用物件には消費税が発生するため、オーナーは適格事業者としてインボイス登録をして、事業用の分に関しては所得税・住民税以外にも、消費税を納税する必要があります。
不動産投資や土地活用で、経営スタイルを選択できるのであれば、賃貸物件は住居用にした方が、消費税の節税になります。
【参照:インボイス制度について】
Q9:経営中のアパートが黒字で税金がすごい。節税対策したい。
A:新たに不動産投資・土地活用することで大きな節税対策ができます。
ローン返済が終わる頃のマンションやアパートは、減価償却もほぼ残っておらず、大きな経費になるものがないため黒字化しやすくなります。さらに、オーナーに給与所得がある場合には、不動産経営の利益と合わせた累進課税により所得税率が跳ね上がることがあります。
このような場合は、税金の仕組みである損益通算を上手に利用して、意図的にマイナスを作り出しながら、資産を拡大する節税対策を導入します。たとえば、新規にアパート経営のために土地建物の両方を購入する、複数の投資用区分マンションを購入するなどで、新しくローンと減価償却の要因を作り、すべての不動産の損益通算によって節税をはかります。
【参照:国税庁 所得税の税率】
【参照:国税庁 損益通算】
Q10:不動産投資・土地活用の相談ができる不動産会社を探したい
A:なるべく多くの不動産管理会社を比較してください。
不動産投資も土地活用も、節税メリットをおさえながら、賃貸経営で長期的に良い結果を出すためには、不動産経営のプロフェッショナルのサポートが必要です。スタート時点から経営・管理までをトータルに支えてくれる、信頼と実績のある不動産管理会社の存在があれば、良い経営につながりやすくなります。
現在、賃貸管理や建物管理を不動産管理会社に委託しているのであれば、節税の観点から、他の管理会社候補探しもしてみてください。同じ管理費を支払うのであれば、より提案力・営業力のある管理会社であるほうが、結果的には節税につながります。
管理会社探しは、たくさんの管理会社に管理プラン請求をして、仕事内容や社員の仕事ぶりを比較してみる必要があります。NTTデータグループの運営する「賃貸経営HOME4U」の一括プラン請求であれば、不動産投資・土地勝代のどちらでも、適切なアドバイスとサポートをしてくれる、信頼と実績のある、良質な不動産管理会社が見つかります。
まとめ
不動産投資と節税について、はじめての不動産投資・土地活用をする方でもわかるように、優しくまとめました。不動産投資で節税ができるのは、固定資産税・所得税と消費税、相続税・贈与税であることがわかりました。
とくに、相続税に関しては、不動産投資と土地活用のどちらであっても、大きな節税効果が期待できることがわかりました。節税対策には、税務と法律の両方に詳しく、さらに不動産経営にも知見のある、信頼と実績のある不動産管理会社とのパートナーシップが大切です。まずは、複数の管理プランを比較するところからスタートしてください。
賃貸経営・土地活用の
相談をしたい方はこちら
複数の会社にまとめて相談